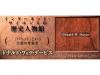「@」の採用と標準化
トムリンソンは、ユーザー名とホストマシン名を識別するために、両者の間に@(アトマーク)を挿入し、メールアドレスを「ユーザー名@ホスト名」と表記した。@は米国では単価を示す記号だが、かれはテレタイプの12個の記号から、ユーザー名に使われることがない識別子として@を選んだ。かれは、SNDMSGのソースコードと利用法を説明した文書をARPANETに送信した。この電子メールでは、リモートホストのユーザーがログインすると着信を確認でき、READMAILコマンドでメールをCRTディスプレイかテレタイプで読むことができた。
ARPAのロバーツはこのメール送信ソフトウェアを評価し、BBNはTENEXの次期バージョンに組み込むことになった。このTENEXは72年3月にリリースされ、ロバーツは4月にARPA局長のスティーブ・ルーカジクに使うように薦めた。ルーカジクはメールソフトウェアをしばらく利用し、READMAILコマンドの使いにくい点を指摘した。ロバーツは72年7月に、TECOのマクロを使用してメールボックスに受信したメールをリスト表示し件名、日付でソートでき、転送・ファイル保存・削除が行えるRDという最初のユーザー用ソフトウェアを記述した。
RDにより国防省では電子メールを業務に使用するようになり、ARPANETのホストコンピュータの半数以上がPDP-10であったため、SNDMSGとRDによるメール送信はARPANETの総通信量の75%を占めることになった。
NWGは1972年4月に、MITのアベイ・ブシャンが中心となり開発を進めていたFTP(File Transfer Protocol)の仕様を見直す会議をMITで開催し、トムリンソンとワトソンが出席しメール機能の実現方法が検討された。FTPの仕様は72年7月のRFC354で発表され、APPENDコマンドでメールを実現することを記していた。しかし、ブシャンが8月に発表したRFC385では、MLFL(Mail File)とMAILコマンドを導入し、ASCIIテキストファイルをFTPデータチャネルでユーザー名に送信する方法に変更した。
SNDMSGでは送信先のファイルシステム内のユーザーのメールボックスの場所を知っている必要があった。MLFLではメールボックスは受信側のシステムが名前で管理でき、異なるOS間でもメールが使える可能性が開けた。BBNのロバート・クレメンツは72年秋にSNDMSGをMLFLコマンドに対応させ、MULTICSではFTPと組み合わせたメールプログラムNETMLが実装された。NWGは73年2月の会議で、FTPのメールアドレス表記に「ユーザー名@ホスト名」を正式に採用した。
トムリンソンはブシャンともにメール・ヘッダーの標準化に取り組み、73年9月5日にRFC561を発表した。この標準化では全ての電子メール・メッセージは、FROM、SUBJECT、DATEの情報を最初に記載することを定めていたが、TOフィールドはなかった。
メーラーの誕生
SNDMSGとRDはテキストエディタの行削除機能によりメールを消去していたが、73年にロバーツの部下のバリー・ウェスラーはNDを書き直し、複数のメール・ファイルの検索と削除を可能にしNRDと名づけた。ARPAのプログラム・マネジャーのスティーブ・クロッカーは、南カリフォルニア州立大学を卒業してARPAのインターンになったマーティン・ヨンクにNRDのコードを改良させた。ヨンクは送受信機能を統合し、コマンドの頭文字か続く2文字目をタイプして「?」と入力するとコマンドの選択肢を表示するメーラーを開発し、BANANARD(バナナRD)と名づけ74年に配布した。
南カリフォルニア大学でBANANARDの開発を手伝ったジョン・ヴィタルは、自発的に機能強化に取り組み75年にMSGを開発した。そして、ヴィタルは76年にMSGを携えてBBNに入社した。MSGは30のコマンドを備えたユーザー向けソフトウェアで、プログラマでなくても利用できるほど使いやすさを追求していた。
MSGの最大の特徴は「answer」コマンドで、受信したメールアドレスと件名を入力し直すことなく返信用に使うことができた。これにより、入力の手間がなくなり、会話する手軽さでメールが使えるようになった。また、「forward」コマンドで別のユーザーに転送することもできた。ヴィタルは「cc(carbon copy)」と「bcc(blind carbon copy)」も考案した。MSGは今日的なメーラーの機能をほぼ完備し、ARPANETで最も利用されるユーザーソフトウェアとなった。
トムリンソンは、2000年4月にアメリカン・コンピュータ・ミュージアムからジョージ・スティビッツ・コンピュータ・パイオニア賞、2004年にIEEEインターネット・アワードをデイヴ・クロッカーとともに受賞した。
参考文献
Daniel G. Bobrow, Jerry D. Burchfiel, Daniel L. Murphy, Raymond S. Tomlinson「TENEX, A Paged Time Sharing Syste, for the PDP-10」Bolt Beranek and Newman Inc. Computer Science Division, Cambridge, Massachusetts 02138 http://www.opost.com/dlm/tenex/tenex72.txt
Raymond Tomlinson「The First Network Email」http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/firstemailframe.html
Daniel L. Murphy「Origins and Development of TOPS-20」1989 http://www.opost.com/dlm/tenex/hbook.html
Craig Partrige「The Technical Development of Internet Mail」BBN Technologies http://www.ir.bbn.com/~craig/email.pdf
Tom Van Vleck「The History of Electronic Mail」February 1, 2001 http://www.multicians.org/thvv/mail-history.html
Dave Crocker「Email History」http://www.livinginternet.com/e/ei.htm
「Ray Tomlinson」http://www.answers.com/topic/ray-tomlinson
「インターネット・サイエンスの歴史人物館」は、今回で最終回です。長い間、ご愛読いただき、ありがとうございました。