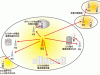802.16e-2005のハンドオーバー機能
【1】サービングBSとターゲットBS
ハンドオーバー(基地局切り替え機能。ハンドオフとも言う)機能は、複数のBS(Base Station、基地局)で構成されるエリア内を端末が移動する場合、現在通信を行っているBS(「サービングBS」と言う。現在端末にサービスを提供している基地局)から、隣接するBS(「ターゲットBS」と言う。端末が移動しこれからサービスを提供する予定の基地局)に通信を維持しながら無線リンクを切り替える機能である。
IEEE 802.16e-2005ではレイヤ2のハンドオーバーの機能として次の4種類のハンドオーバー方式が標準化されている。
【2】定義された4つのHO(ハンドオーバー)の方式
(1) Break-Before-Make HO
サービングBSとの通信を切断した後、ターゲットBSとのサービスを開始するハンドオーバーである。移動端末(MS:Mobile Station)に関する情報などを無線インタフェース以外にネットワーク・インタフェースを介しても交換する方式である。オプティマイズドHHO(Hard Hand Over、基地局の切り替え中に物理層が一旦切断される方式のハンドオーバー)もこの分類に含まれる。
(2) Make-Before-Break HO
サービングBSとの通信を切断する前に、ターゲットBSとのサービスを開始するハンドオーバーである。
(3) Fast-BS-Switch (FBSS)
リンク品質を向上させるためにBS(基地局)の切り替えに対して、高速な切り替えメカニズムが適用されたハンドオーバーである。移動端末(MS)は、アクティブ゙な1基のBS(アンカーBS)と送受信するフレームのみを処理し、他のBSからのフレームを同時には処理しない。
アンカーBSの変更は、フレーム単位での切り替えが可能な程度に高速に行われる。アンカーBS(基地局)とは、サービングBSの機能を備えていると同時に、ホーム・エージェント(ユーザーのホーム・ネットワーク上にあるルータ)とも接続されており、インターネット接続ができる基地局のことである。
(4) Macro Diversity Handover (MDHO)
下り回線では、2基以上の複数のBSから同時に同一のMAC PDU(プロトコル・データ・ユニット、MAC層で扱うデータの単位)が1台の端末向けて送信され、端末では複数の基地局から送信されたMAC PDUをそれぞれ受信して最大比合成などダイバシチ合成に類する処理を行う事で、無瞬断の基地局切り替えが行われる。上り回線では、1台の端末からのMAC PDUが複数のBSで同時に受信(復調・FEC復号処理)され、基地局間で合成処理が行われるハンドオーバーである。
スリープ・モード/アイドル・モードを規定
IEEE802.16e-2005では、通信を実行していない端末の管理モードとして、スリープ(Sleep)モード(休止状態)と(Idle)・モード(待ち受け状態)の規定が追加された。端末はこれらのモードを実装することによって、非通信時間帯の消費電力の軽減を図ると伴に、BSにおいては端末管理の負荷の軽減が期待される。
(1) スリープ・モード
スリープ・モードは、ネットワーク・エントリー(登録)を完了している端末が、サービングBSとの無線リンクが接続されておらず、移動端末(MS)がBSからの送信情報を受信できない期間の管理モードであると定義している。
スリープ・モードを利用することで、端末は消費電力を最小化することができるとともに、BS側では無線インタフェースのリソース(帯域など)の節約となる。スリープ・モードの実装は、移動端末(MS)に対してはオプションの扱いであるが、BSには必須事項として指定される
(2) アイドル・モード
アイドル・モードは、移動端末(MS)がBSとの接続を切断した後、下り回線のブロードキャスト・メッセージのみを受信可能とするモードとして定義している。アイドル・モードに移行した端末の情報は、ページング(端末の呼び出し)制御機能で管理し、BSにおいては負荷軽減に寄与する。
アイドル・モードに移行した端末向けのデータをBSが受信した場合、BSは端末のMACアドレスを含むブロードキャスト・ページングによって端末を呼び出し、ページングを受信した端末は、直ちにアイドル・モードを終了してネットワークに再エントリー(再登録)を行い、通信が可能な状態に遷移することでアクティブな状態となる。
(つづく)