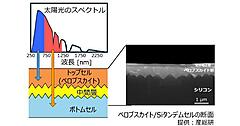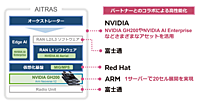放送・通信融合時代を迎えた今日、その現状と課題について、慶應義塾大学 環境情報学部 村井純教授と早稲田大学 大学院 国際情報通信研究科 亀山 渉教授に対談を行っていただきました。
これまでの、
『<テーマ1>放送と通信はどこがちがうのか?』
『<テーマ2>放送と通信の技術的課題は何か?』
『<テーマ3>放送・通信融合時代の制度的・政策的な課題は何か?』
につづいて、今回は最終回として、
『<テーマ4>デジタル時代の知的財産権とは何か?』
についてお話いただきました。(文中、敬称略)

慶應義塾大学 村井 純 教授 VS 早稲田大学 亀山 渉 教授
テーマ4
デジタル時代の知的財産権(知財)とは?
【1】根本的に「知財とは何か?」を見直すとき!
村井 放送と通信の調和に関するもうひとつのキーワードとして、デジタル時代の知的財産権(知財)の問題が注目されています。この問題は、ビジネスに大きな影響を与えますので、デジタル時代を迎えて、根本的に「知財とは何か?」を見直す必要があります。
先にお話ししたように、デジタル化(あるいはインターネット)は、現在起こっていることを原点に戻って、根本的に考え直させるところがあります。「自分とは何だろう?」、大学の授業を全部インターネットでやり始めると「大学とは何だろう?」「どうして授業料をとるのだろう?」と、そういう原点的なところまで議論がきてしまいます。
そこがデジタル化のいいところなのです。人間が惰性でやっているようなことを、ちょっと見直そうというようなところがあるのです。このため、デジタル化時代の「知財とは何だろう?」ということも当然問われてきます。
情報がデジタル化されると、まったく同じ複製を作り出せることになる。それを利用した技術が、先に話したインターネットの動作原理であるパケット交換の信頼性技術そのものなのです。
つまり、どこかでデータを紛失してそれが困るならもう一度送ればいいのです。これはアナログとまったく違うところです。アナログ時代のように、「かけがえのないものがなくなってしまった」というのではなく、「なくなったら捨ててもいい。もう1回送ればいいのだから」というわけです。
—デジタル時代の価値観が必要なんですね。
村井 このような背景からデジタル情報というのは、アナログ情報に対して、かなり価値観が違ってくる可能性が出てきます。それを「知財」(知的財産権)として、どう扱うのか。現在、知財の保護を強く主張する人たちに対して、「もう一度考え直そう!」ということになる可能性があるのです。
すでに、放送というビジネスの中に、アナログ時代につくられた知財に対する考え方やルール、さらに理念もできています。したがって、現在のように、放送がデジタル化されるとき、知財などに対する議論は避けて通れません。今、放送と通信(インターネット)の調和の中でぶつかっているほとんどの項目は、知財と関連している項目なのです。この議論が今後どう発展するか、まさに人類にとって大きな課題に直面しているのです。
【2】テレビとラジオに見る「知財」の具体例
—亀山先生は知財について、いかがお考えですか?

亀山 知財(知的財産権)の話も、実は昔からあった話ではなくて、約300年前の1709年に、イギリスではじめてまとまった著作権法が作られたのが最初といわれています。300年くらいの歴史です。
やっぱり基本的には後から出てきて、作られた制度なのです。ポイントは、今、村井先生がおっしゃったように、デジタル通信では、複製(コピー)は至るところで起こっていまして、複製のない通信はありえないのです。
ところで、映像の複製(コピー)問題の事件としては、近年(2004年)に千葉県松戸で起こった「録画ネット事件」があります。この事件は、ある会社と放送局の間で起きた事件ですが、その会社は、海外にいるお客さんにテレビ・チューナー付きのPC(サーバー)を買ってもらい、そのPCを置くための場所貸しをしている、いわゆるデータ・センターだという位置付けです。
データ・センターは、お客さん(ユーザー)が買ったPCを置いて、電源を供給しています。お客さんは海外にいて、インターネットを通じてPCに録画指令を出し、日本のテレビ放送をそのPCで録画し、それを海外からインターネット経由で視聴するという話なのです。
しかし、これは違法だとしてそのデータ・センター会社は放送局から訴えられました。要するに、ここのデータ・センターが主体となって番組を複製し、録画したものを海外に送るのを幇助(ほうじょ)しているからということになった。録画指示を出しているのはお客さんだとこの会社は主張しましたが、利用者による私的複製とは認められないという判決がくだされました。しかし、結局は和解されたのだそうです。
このようなサービスは、技術的には今や、誰でもあたりまえのようにできるサービスです。したがって、このようなことも含めて、ある基準をつくっていくのは、本当に早急の課題なのです。判例という既成事実が作られてしまう前に、きちんとした法体系の整備が必要と思います。

村井 私がよく使っている例で、NHKの放送50年史の中に載っている、ラジオが昭和3年に最初に相撲中継をしたときの話があります。相撲協会は、そのときも現在と同じように、国技館の入場料や、巡業先の入場料で成り立っているビジネス・モデルです。ところが、相撲人気が落ち、入場者がだんだん減って経営難になってきていた。
そんなとき、NHKがラジオ放送で相撲番組を流すといってきた。これに対して、相撲協会は、猛反対したのです。ただでさえお客が減ってきているのに、相撲の実況を無料のラジオ放送で流したら、相撲協会はつぶれてしまうから「絶対NO!!」ということになった。
ところが6代目出羽ノ海親方が、「いや、もしかしたら面白い相撲の実況を聞いたら、お客さんがくるかもしれない。」と言った。それでやってみようということになり、昭和3年に初めての相撲のラジオ中継が始まったとたんに、土俵近くの升席は超満員になったそうです。
—新しいビジネス・モデルの登場ですね。
村井 そのとおりです。ここから学ぶことはたくさんあります。相撲が「入場料」で成り立っているビジネス・モデルだと思っていると、このコンテンツ、つまり相撲そのものをただで放送するということはありえないわけです。それでラジオという新しいメディアができたときに、そこからどのように契約金をとるのか、放映権をとるのかということが問題になってくる。
一方、そのようなものは無くして、それでお客がたくさん入って儲かるというビジネス・モデルもあるわけですね。音楽業界などは、結構そういうことに早くから気がついていましたね。
ここでは、身近なアナログ・ラジオ放送の例の話をしましたが、現在は、デジタル・メディアとしてのインターネットやデジタル放送などが普及してきている時代ですから、これらの基盤を上手に使って、新しい挑戦をしていくということが、知財の周りにも出てきていると思います。
亀山 私が知っているのはテレビの話でして、昭和28年(1953年)にテレビ放送が開始されましたが、このとき、旅行業界が大反対したのです。まさしく村井先生の話された相撲と同じで、きれいな北海道の景色がテレビで放映されたら、誰も北海道にいかなくなってしまうというのが反対の理由だったのです。まさしく歴史は繰り返すと思いましたね。
村井 本当にそう思います。
【3】注目される2006年と2007年の動き!
—これまで、放送通信の融合あるいは調和について、多角的な視点からお話をいただきましたが、最後に、一言ずつお願いします。
亀山 今後、さらに放送と通信の融合あるいは調和について、対立するという視点からではなく、みんながいろんなことを議論できる状態をきちんと作るということが必要です。強権的に頭を抑えつけるということではなくて、みんながフェアに公平にいろんな意見を述べて、その中で決めていく環境ができれば、一番いいと思います。
村井 私は、もうそういう環境はできてきたように思います。在り方懇では、本当に今まで議論してはいけなかった「タブー事項」が議論の中に出てきました。これは放送と通信の歴史上、画期的なことです。
私の実感として、2006年、2007年は、この放送・通信の調和(融合)の分野は、すごい年になると思いますね。議論のうえからもそうですが、その方向性に対しても大きなきっかけになる年だと思います。
—お忙しいところ、ありがとうございました。
関連リンク
録画ネット
http://www.6ga.net/
録画ネット裁判関連資料(PDF)
http://www.6ga.net/x_gensho.pdf