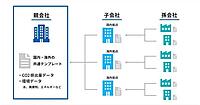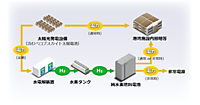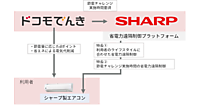NGNの中枢部はSIPで制御
NGNの中枢部はSIPで制御
—NGNはSIPを採用することになっているのですね。

冲中 少なくとも、コネクション・オリエンテッドな電話のような通信の接続制御は、SIPでやるというのがコンセンサスです。(コネクション・オリエンテッド:電話のように相手と接続関係を確立してから行う通信))
そうすると、端末側にインストールされるSIPクライアントというソフトのネットワークとのインターオペラビリティ(相互接続性)をどう確保するか、これが重要になってきます。そのときに、そのSIPクライアントをどこに置く(インストールする)かが問題となります。
すなわち、SIPクライアントを、一番身近なユーザーの端末側に置くのか、あるいは家庭と外部のネットワークを接続するホーム・ゲートウェイに置くのか、あるいはその中間にあるSTB(セット・トップ・ボックス。欄外の解説を参照)に置くのか。要するに、どこに置くかによってシナリオが変わってくると思います。しかし、この問題については必ずしも、業界でコンセンサスができていないのです。
江﨑 むずかしい問題ですね。
冲中 それで、通信事業者側の意識は、どちらかというとユーザー端末ではなく、STB、あるいはホーム・ゲートウェイにSIPクライアントを積む、ということです。つまり、ユーザー端末と家庭の外部のネットワークのインターオペラベティは、そのSTBなりホーム・ゲートウェイ機能で吸収できるのではないかという、期待感はあります。
江﨑 その場合、STBはSIPクライアントがインストールされていて、SIPで通信できるようになっていますね。それで、家庭の中にあるパソコンや情報家電というのは、SIPをインストールするのですか、しないのですか。いかがでしょうか?
冲中 そこは、正直いってまだ決められていないところです。個人的にはSTBにSIPクライアントを積むということになると思います。
江﨑 その場合は、NGN上にあるSIPサーバと、家庭にあるSTB(SIPクライアント)の間のSIP通信ということになりますね。しかし、電話とか、区別されたビデオ配信とかは、STBごとではなくて、別のやり方で通信するのではないか、そういうアーキテクチャになるのではないかという気がしているのです。そうしないと多分、システムとして拡張性がないし、また、全部キャリアSIPにしてしまうとキャリアのSIPサーバは処理しきれなくなり、確実に死ぬと思います。
そうするとNGNでは、今のインターネットと非常に近い形で、ユーザー端末を認証したあと、ルーティングやフローの制御(パケットのバッファ溢れが起こらないようにする制御)、優先制御(QoS)ができるようなパス(通信路)の提供を、STBあるいはユーザー端末に対して直接SIPで通信できるようにすべきではないでしょうか。
そのときのパケットのフローは、あるポリシーにしたがって選択されたプロバイダ(ISP)の回線を使用して相手に届く、というシナリオではないかというという気がするのです。
冲中 ビデオ配信をどうするかについては、まだはっきりしないところがあります。ビデオ配信もある種のQoSのポリシーが要るのです。個々の、つまり、あるストリーム・サーバと、実際のユーザー端末の間で、どうそのポリシーをネゴシエート(折衝)するかという場合に、そこではSIPを使わざるをえないような気もします。
江﨑 そうだと思います。SIPは、いろいろなシグナリング(信号制御)プロトコルのうちの一つなのです。つまり、SIPは通信の品質制御をするために、現在用意されたひとつのプロトコルなのです。このSIPによって、ポリシーを反映させたルーティングと、それからIPアドレスの解決(Resolution)も行ってくれる。さらに、パケットの経路制御も実質的にSIPサーバでやってくれるので、うまくいくというシナリオかなと思います。
そうするとですね、そこまでステップバックしてNGNのシステムをみると、NGNは、実はインターネットそのものなのですよ。つまり、グローバルなコネクティビティ(接続性)をきちんと提供するためのIPアドレスがあって、あるパケット・フローに対して、ルーティングのインテリジェンスを持たせるためにSIPが存在している。
そのどちらを選ぶか(キャリアSIPを選ぶか、現在のインターネット的SIPを選ぶか、あるいはSIP以外のサービスを選ぶのか)というのは、実は、アプリケーションでも、STBでも、あるいはPCでも、自由に選択できるようなアーキテクチャになっていくべきなのだろうと考えています。