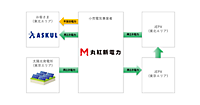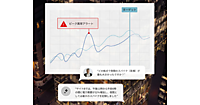NGNで重要なSIPサーバの相互接続
NGNで重要なSIPサーバの相互接続
—最後に、NGNはこれからどのように展開していくのか、展望などを一言ずつお話いただけますか?
冲中 すでに申し上げましたけれど当社は、固定網については、まだNGNではありませんが、すべてSIPベースに変えしまおうとしています。技術的に大きな障害にぶち当たらなければ、2008年には固定系は全部SIPになっています。
問題は、そのときに、うちからNTT網に出て行くところをどうするのかというところが残っています。そのころ、NTTさん側はまだSIPになっていないでしょうからね。NTTさんのネットワークは、私どものものよりずっと大きいですから。
そこで、どうしても既存の電話網で使用されているナンバー7(No.7共通線信号方式、用語解説参照)との相互接続が必要になってきます。
一方、移動系のSIP化(IMS)というか、IP化というのは、どうしてもネットワークが大きすぎてしまうため、ペースがのろいのです。本当にSIPベース(あるいはIMSベース)で、移動系と固定系の両方の運用を一部始められるのは、2008年になるかどうかというところです。
江﨑 するとですね、私たちが今、冲中さんにもいろいろお手伝いいただいている、SIPの相互接続試験(注1)は、ものすごく重要な試験になると思うのですよ。
注1:VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース
2004年12月にJPNICを事務局とし、WIDEプロジェクト、IPv6普及高度化推進協議会主要ISPや関係諸団体を発起人として設立されたコンソーシアム。ISP-ISP、ISP-CPE(宅内機器)、ISP-TE(端末)でのSIPを用いたVoIPシステムの相互接続性を確立することを目的とする。

お話のように、NTTが遅れるとすれば、多分、オーバーレイ(仮想ネットワーク。用語解説参照)の形でSIPに対応させることになると思うのです。そのときに、それがきちんと初めからつながり、NTTの本番のNGNのSIPサーバが、同じ仕組みのSIPサーバなってくれれば、それが一番いいパターンだと思っています。
現在は、仕様と実装が揃っていないため、残念ながらKDDIさん用のSIPサーバと、NTTさん用のSIPサーバと、その他ISPさんのSIPサーバはまったく異なった仕様・実装となってしまう可能性もあるわけですね。これは体力消耗戦ですね。
ですから、ベンダにとって見れば、それらの問題に対処し、解決できるように、今から2008年に向かって試験をやっておかなくてはならないのです。
それから、無線(ワイヤレス)系が遅れるというのはおっしゃるとおりでが、ワイヤレス系の場合は、結構高速なインタフェースのものがいくつか出てきています(例えば802.11nとかWiMAXなど)。ですから、多分、そちらが先にオーバーレイ(仮想ネットワーク)の形でSIPに移行していくのではないかなという気はしますね。
—いずれにしても、NGNを実現する上で、このSIP(IMS)の相互接続というのが、これからすごく重要なテーマになるのですね。
冲中 おっしゃるとおりです。具体的にこれと一番近いことをやっているのは、TISPANなのです。
江﨑 私も、非常に重要なテーマと考えています。具体的には、3GPPが仕様化しているIMSベースで、相互接続を実現しようと考えています。
完
用語解説
TISPAN:Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks、欧州の電気通信関連の標準化団体であるESTI(European Telecommunications Standards Institute、欧州電気通信標準化気候)のプロジェクトの一つ。最近ではNGNの標準化を目指したプロジェクトとして有名(2003年に設立)。
E.164:ITU-TのEシリーズ勧告の1つで、国際公衆電気通信に関する番号計画。E.164は、ISDN番号を規定し、番号の桁数は最大15桁で次のような構造とになっている。<例>東京の電話番号03-5275-1087(インプレスR&Dの電話番号)を国際公衆電話番号にする場合は、日本の国番号は81であり、市外局番03の0をとって3とし、加入者番号が5275-1087なので「81-3-5333-0851」となる。
No.7共通線信号方式:Common Channel Signaling System No.7、SS7とも略記される。現在運用されている、キャリアのネットワーク内の電話交換機を相互に接続する場合に、電話番号や認証情報、課金情報などのサービス 管理情報をやり取りする信号(シグナリング)方式(通信を開始する際の手順)。
オーバーレイ:仮想ネットワーク。例えば昔のモデムのインターネットは、仮想ネットワークの一例である。つまり、電話の上に、IPを乗せてインターネット接続していた。
プロフィール

江﨑 浩
東京大学 大学院
情報理工学系研究科 教授
WIDEプロジェクト
ボードメンバー
MPLS-JAPAN代表
IPv6普及・高度化推進協議会
専務理事
略歴
1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程了。工学博士(東京大学)。
1987年 (株)東芝入社 総合研究所にてATMネットワーク制御技術の研究に従事。
1990年より2年間 米国ニュージャージ州 ベルコア社客員研究員
1994年より2年間米国ニューヨーク市 コロンビア大学客員研究員。高速インターネットアーキテクチャの研究に従事。
1994年 MPLSのもととなるCSR(セルスイッチルータ)技術を IETFに提案。その後、セルスイッチルータの研究・開発・マーケティングに従事。IETFのMPLS分科会、IPv6分科会で標準化活動に貢献。
1998年10月より東京大学大型計算機センター助教授、2001年4月より東京大学 情報理工学系研究科 助教授。
2005年4月より現職(東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授)

冲中 秀夫
KDDI株式会社
執行役員 技術渉外室長
略歴
1977年 早稲田大学大学院修士課程修了(物理学および応用物理学)
同年 国際電信電話(株)入社
1991年まで研究所にてディジタル移動衛星通信システムの研究開発
1986~1988年 インマルサット事務局にてInmarsat-M/Bシステム開発
1991~1994年 DDIにてPDCシステム開発
1994~1999年 KDDにて海外移動通信事業開発、IMT-2000事業企画等
1999年 DDI入社、移動体通信本部事業戦略部長
2003年 執行役員 au事業本部 au事業企画本部長
執行役員 技術統轄本部技術企画本部長
執行役員 技術企画本部長(組織変更)
執行役員 技術渉外室長
工学博士(早大、1986年)。1999年電子情報通信学会森田賞、業績賞受賞。2005年日本ITU協会功績賞受賞。現在WiMAX Forumボードメンバー。3GPP2 Steering Committee議長、3GPP2 Services and Systems TSG議長、MWIF Board of Directors、早大非常勤講師等歴任。