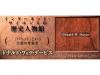ALOHANETとEthernet
ALOHANETの開発グループのクリストファー・ハリソン(Christopher Harrison)は、インテルが1972年に開発した8ビット・マイクロプロセッサのi8080でTCUを設計し直し、メモリを拡大して全二重通信を可能にし、さらに通信プロトコルをソフトウェアで記述できるようにした。新型のTCUは、プログラマブル・コントロール・ユニット(PCU)と名づけられた。また、ロバーツが提案した時間スロットを実装した同期ステーションも開発され、チャネルの利用効率は36%に向上した。
これでも利用効率は決して高いとは言えず、ハーバード大学の大学院生だったロバート・メトカフ(Robert M. Metcalfe)は、1973年にパケットを送信する前にチャネルが空いているか確かめるアルゴリズムを考案した。この手法は、中央に交通整理をする仕組みがなくてもチャネル利用効率を80%に向上でき、メトカフがゼロックス・パロアルト研究所で開発したEthernetの基本技術になった。メトカフは、ARPAのプログラム・マネジャーだったスティーブ・クロッカー(Stephen Crocker)からエイブラムソンの論文を紹介され、ハワイ大学を訪れALOHANETの通信プロトコルのソフトウェア開発を担当していたリチャード・バインダー(Richard Binder)と3ヶ月間仕事をした。
ラリー・ロバーツは1972年春の合同コンピュータ会議で「パケット通信技術の発展としての携帯個人端末について(Extensions of packet communications technology to a hand held personal terminal)」を発表し、現在のモバイル・インターネットの世界を予見していた。
国際衛星通信の広がり
BBNでIMPの開発に携わり72年にARPA情報処理技術部に移籍したロバート・カーン(Robert Kahn)は、ロバーツの意志を継いでパケット無線のプロジェクトを推進し、サンフランシスコ湾を囲む地域でPRNET(Packet Radio Network)を立ち上げ、さらにSATNETにより北米と欧州を衛星で結ぶパケット通信網を形成した。
エイブラムソンは72年に国連の諮問委員となり、発展途上国が衛星通信を活用できるように、ハンガリーのブタペスト、インドネシアのジャカルタ、フィリピンのマニラなどで1987年まで通信網の立ち上げにかかわった。エイブラムソンはこの間に、スペクトラム拡散方式による無線通信の回線容量の利用効率の向上に取り組んだ。スペクトラム拡散でユーザ数の拡大を可能にしたALOHANETの仕組みは、静止衛星と多数の60cmから100cmのアンテナが交信するVSAT(Very Small Aperture Terminal:超小型地球局)の基本技術となり、1980年代にCバンドとKuバンドを利用する商用ユーザを大きく拡大した。
エイブラムソンは1980年に米電気電子技術者協会(IEEE)のフェローに選ばれ、1995年にIEEE Koji Kobayashi Computers and Communications Awardを受賞した。かれは1993年に編者となりIEEEプレスから出版された「多元接続通信(Multiple Access Communications: Foundations for Emerging Technologies)」は、LAN、地上局無線、衛星を利用したパケット通信における多元接続技術を包括的に扱い、パソコンや携帯電話などによるインターネット利用の拡大を基礎づけた。
衛星インターネット・サービス
エイブラムソンは1996年にハワイ大学を引退し、カリフォルニア州サンフランシスコにALOHAネットワークス社(ALOHA Networks, Inc.)を創立した。この企業はベンチャーキャピタルの出資を得て、スペクトラム拡散方式の双方向衛星通信のスプレッドALOHA多元接続(SAMA: Spread ALOHA Multiple Access)を活用するSkyDSLにより、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)に電話回線とは異なる選択肢を提供することを意図していた。
インターネットの利用が家庭に急速に普及し始め、数多くのISPがサービスを開始したが、家庭や企業にサービスを提供するためには電話会社が独占する回線を利用せざる得なかった。衛星通信は電話回線より利用料金が格段に高いという印象が強かったが、ALOHAでは返信がブロードキャストであるため回線が混み合うことがなく、送信のランダムアクセス回線では接続手続きなしでセッションを張れ、スペクトラム拡散により多数のユーザをサポートすることが可能になった。ALOHAネットワークスは、Kuバンドを利用して衛星の中継器あたり60,000以上のユーザにグローバル・インターネット・サービスを提供することができた。
ALOHANETは当初から通信の上がり下がりが非対称で、通信速度も上がり下がりを独立して柔軟に設定できる。携帯電話の世界ではCDMA(Code Division Multiple Access:符号分割多元接続)を実現する上でALOHANETを参考にして研究を続け、欧州の携帯電話の標準となったGSM(Global System for Mobile Communications)の次世代標準として2003年に移行が始まったUTMS(Universal Mobile Telecommunications Systems)では、SAMAの技術が携帯電話の性能向上を実現する上で土台を提供した。
エイブラムソンは、2000年度のエドワード・ライン・テクノロジー賞(Eduard Rhein Technology Award)を受賞した。この賞はドイツの出版社社長エデュアルド・ルドルフ・ライン(1900ー1993)により、テレビ技術に対する貢献者を讃えるために1976年に設けられたが、1990年に受賞対象を情報分野の基礎研究と文化への貢献に広げた。1991年に情報理論のクロード・シャノン、98年にWWWのティム・バーナース・リーが受賞している。
参考文献
Janet Abbate「Inventing the Internet」The MIT Press 1999
N. Abramson, "The Aloha System-Another Alternative for Computer Communications," Proceedings of Fall Joint Computer Conference, AFIPS Conference, p. 37, 1970.
N. Abramson, "Development of the Alohanet," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-31, No. 3 (Mar. 1985), pp. 119-123. http://www.eng.tau.ac.il/~meir/advcn/abramson_ALOHA.pdf
R. Binder, N. Abramson, F. Kuo, A. Okinaka, D. Wax「ALOHA Packet Broadcasting: A Retrospect」 http://research.microsoft.com/~gbell/Computer_Structures_Principles_and_...
Muriel Medard, Jianyi Huang, Andrea J. Goldsmith, Sean P. Meyn, Todd P. Coleman 「Capacity of time-slotted ALOHA packetized multiple-access systems over the AWGN channel」http://web.mit.edu/medard/www/ALOHA_rev61.pdf