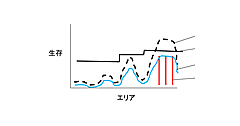今後想定されるビジネスモデル
今後想定されるビジネスモデル
今後ビジネスモデルとしては、プレイヤーごとに下記のようなものが想定される。
1.自治体などのビジネスモデル
地方自治体は、スポンサーおよび、災害・有事の際にオペレータ(運営者の役割)を担う。
オペレータの直下層に位置するユーザーを「ホットスポットオペレータ」と定義し、想定される団体は、商工会、商店街、町内会、大企業なども含む。
- 自治区の公共施設をメッシュポイント(メッシュの拠点)として、前述した3Wi-Fi APとインフラ敷設を行う。
- 地方自治体は、このような機能をもつAPを購入する団体が「自治体が災害・有事にAP を使用」を許諾した場合にキャッシュバックを行う。
- 必要があれば、キャシュバックはAPレンタルやレンタルOEMにも拡充させる。
2.レンタル OEMのビジネスモデル
APの販売を担当する組織である。民生品の価格競争を促す目的でマルチベンダー化する。
- ベンダーはファームウェア(FW)パッケージの提供を受け、APに実装し販売案配する。
ファームウェア(FW)パッケージとは、今回の機能をもつWi-Fiの追加ソフトウェア群のことである。 - 「自治体が災害・有事にAP を使用」する許諾書に製品名を明記することでキャシュバックを受ける。
3.ユーザーのビジネスモデル
ユーザーとは、自宅などでWi-Fiを利用する個人を指す。
- 本APをレンタルショップから購入する。
- APを自宅などのインターネット回線に接続し、平時は個人利用のルータとして使用する。
- 購入時に「自治体が災害・有事にAP を使用」を許諾した場合に、キャッシュバックを行う。これによって、一般に市販されているAPとの価格差を相殺させる。
これらの仕組みによって、自治体の「自衛通信網設置予算」を奨励金とする。
家庭にも、これらの機能をもつAPを設置することによって、とくに住宅密集地域や大商業地域などには、よりきめ細やかな面的な自営無線システムの準備が整備される。