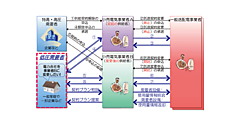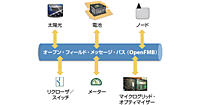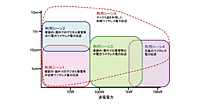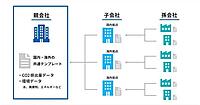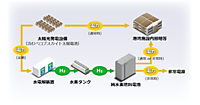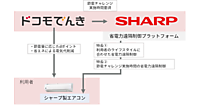ISO/IECやSGIP委員会との協調して標準化へ
― IEEE 1888.3のセキュリティ強化規格も承認へ ―ISO/IECやSGIP委員会との協調して標準化へ
現在、IEEE標準策定委員会(IEEE-SA:Standard Association)からの働きかけで、ISO/IEC JTC1/SC6/WG7(「通信とシステム間の情報交換」に関する標準の策定委員会)において、IEEE 1888の仕様について議論が行われている。
2013年2月には、JTC1/SC6/WG7の最初の電話会議が開催され、その後、6月後半のソウル会合で今後について話し合われた。SC6/WG7では、DCM(Device Control and Management、機器制御と管理)プロトコルと呼ばれる機器制御仕様の策定が行われていた。
ソウル会合では、IEEE 1888とDCMとの間の違いが焦点となったが、これらの間には目的やアプローチなどに明確な差異があること判明したため、会議での合意のもとに、IEEE 1888ワーキンググループとSC6/WG7は、協調して標準化を進めていくことになった。
今後、2013年10月に開催されるWG7の中間会合において、ISO/IEC標準に向けた話し合いが行われる。
また、SGIP(注1参照)のBuilding-to-Grid/Industrial-to-Grid合同ワーキンググループと東大グリーンICTプロジェクトは、2009年からこの分野で共に活動しており、IEEE 1888は、SGIPのCatalog of Standards(CoS注8)候補に挙がっている
IEEE 1888検査仕様の策定と検査装置(テスター)の開発
このIEEE 1888プロトコルについて、現在、東大グリーンICTプロジェクトが中心となり、IEEE 1888プロトコル適合性検査仕様(ドラフト)の作成が行われている。かつて、2010年の総務省系プロジェクトにおいて、適合性検査仕様の開発が行われていたが、その後、IEEE 1888の相互接続試験や運用数の増加に伴い、IEEE 1888プロトコルに対するノウハウが蓄積されてきた。そこで、これらのノウハウに基づいて、プロトコル検査仕様を充実させることになった。
IEEE 1888プロトコル適合性検査仕様は、その機器またはソフトウェアが正しくIEEE 1888を実装しているかどうかを検証するテストケースの集まりである。
〔1〕検査仕様はテストケースの集まり
例えば、「最新値のデータを要求する電文をそのソフトウェアに渡したときに、返答される電文の中身が正しいかどうか(ここには、いくつかの確認ポイントがある)」は、1つの「正常系」のテストケースとなる。あるいは、「本来、要求の電文に含む必要のある内容が欠けていた場合に、正しくエラー応答を返してくれるかどうか」も、1つの「異常系」のテストケースとなる。
これらのテストケースのセットを適合性検査仕様とすることで、IEEE 1888機器・ソフトウェアを検査する統一的な基準ができる。
〔2〕検査装置(テスター)の開発
一方で、このような検査仕様の策定作業と同時に、検査装置(テスター)の開発を進めている。
図2に示すように、検査装置は、検査対象との間で検査仕様に従って通信を行い、その結果をレポートとしてまとめる機能をもっている。このレポートを、IPv6 Ready Logoプログラム注9や、ICAP注10のような認定プログラムで審査することによって、プロトコル適合性認定が行われることになる。IEEE 1888プロトコルについては、どのプログラムで実施されることになるかは、現在、議論中である。
図2 検査装置によるIEEE 1888機器/ソフトウェアの試験の概念図

また、検査仕様が充実され、検査体制が整うことによって、IEEE 1888機器・ソフトウェアの品質向上を図ることができる。この検査を通過したものは、互いにIEEE 1888のプロトコルで接続できるため、エンジニアリングの現場で安心して利用できる。
〔3〕IEEE 1888の検査仕様の内容
現在、IEEE 1888の検査仕様には、以下の項目が盛り込まれる予定である。
- 検査対象となる実装クラスの規定
- HTTP通信に関する共通検査項目
- SOAP/XML通信に関する共通検査項目
- FETCH(データの読み出し)サーバに関する検査項目
- FETCHクライアントに関する検査項目
- WRITE(データの書き込み)サーバに関する検査項目
- WRITEクライアントに関する検査項目
- TRAP(イベント登録・配信)サーバに関する検査項目
- TRAPクライアントに関する検査項目
- TRAPコールバックに関する検査項目
- LOOKUP(探索)サーバに関する検査項目(2013年8月以降に着手開始)
- LOOKUPクライアントに関する検査項目(2013年8月以降に着手開始)
- REGISTRATION(登録)サーバに関する検査項目(2013年8月以降に着手開始)
- REGISTRATIONクライアントに関する検査項目 (2013年8月以降に着手開始)
なお、検査仕様のドラフトは、2013年の夏中にIEEE 1888のワーキンググループ内で共有され、現在進められている検査装置に実装される予定となっている。
▼ 注1
SGIP:Smart Grid Inter-operability Panel、米国スマートグリッド委員会。NIST(米国立標準技術研究所)の管轄にあったSGIPは、2012年7月、SGiP 2.0 Business Sustainment Plan(SGiP 2.0 ビジネス維持計画:将来のスマートグリッドの相互運用性に関するロードマップ)として独立した組織「SGiP 2.0 Inc.」となり、従来の「SGIP」から移行した。
▼ 注8
CoS:Catalog of Standards、スマートグリッドを構築するうえで必要と思われる規格を、NISTが主導で選択し掲載したカタログのこと。ここに掲載されることは、IEEE 1888を普及させるうえで大きな力となる。
参考URL http://wbb.forum.impressrd.jp/feature/20111216/862〕
▼ 注9
IPv6 Ready Logoプログラム:国際的なコンソーシアムであるIPv6 Forumは、IPv6の展開のための技術指導を提供することを最重要点とするともに、唯一の世界的なIPv6 Ready Logoプログラム(適合および相互接続試験からなる)を開始している。IPv6 Ready Logoプログラムは、IPv6が今すぐに有効で、使用する準備ができていることを明らかにすることによって、ユーザーの信頼を大きくすることを目的とする適合および相互接続試験である。
▼ 注10
ICAP:IEEE Comformity Assesment Program、IEEE の適合性評価プログラム。