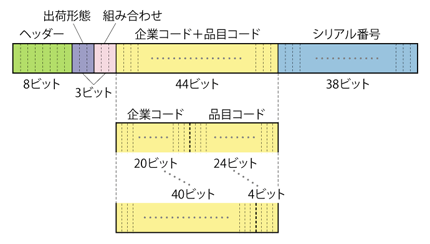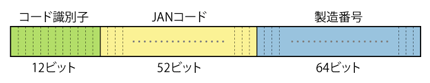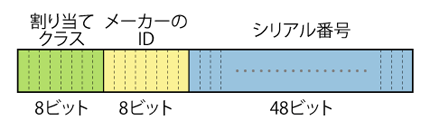代表的な3つのID体系
EPCglobalやT-Engineフォーラム(本連載の第1回 を参照)が提唱するRFIDシステムでは、RFIDタグに記録されたIDを参照して、そのIDと対応する情報を参照したり、対応する情報に新たな情報を追加したりします。
現在は、EPCglobalのEPC、ユビキタスIDセンター(T-Engineフォーラム)のucode、ISO/IEC 15963の3種類が代表的なID体系と考えられます。次に、それぞれのID体系の仕様を説明します。
【1】EPCglobalのEPC
EPCは、JAN(Japan Article Number、欄外の用語解説参照)などの商品コードを拡張したような体系となっており、現在は64ビット、または96ビットが規定されています。96ビットの場合、先頭8ビットがヘッダーで、続く3ビットが出荷形態(パレット、ケース、個々の商品など)を識別する数値、次の3ビットが企業コードと品目コードの組み合わせを表す数値、次の44ビットが企業コードと品目コードで、44ビットのうち20~40ビットが企業コード、44ビットのうち4~24ビットが品目コードです。
そして、残りの38ビットがシリアル番号(連番)で、製品などに一つ一つ異なる番号が振られます。なお、8ビットのヘッダーは、コード全体の長さ(64ビットまたは96ビット)、コード体系の種別(企業間の流通に使用する、企業内の資産管理に使用する、用途を限定しないなど)を表しており、値があらかじめ規定されています。
【2】 ユビキタスIDセンター のucode
ucodeは、基本ビット数が128ビットですが、必要に応じて128ビット単位で256ビット、384ビット、512ビットというように拡張できます。EPCとは異なり、原則としてコード自体には意味がなく、ユニークな番号であればよいとされています。

写真12 ucode実証実験の模様(2004年)
このため、他のコード体系を包含することが可能です。例えば、13桁のJANコード(1桁あたり4ビットで合計52ビット=13 x 4)を包含する場合、先頭の12ビットに、13ビット目以降で表現するコードがJANコードであることを表すコード識別子を記述します。
13ビット目から64ビット目までの52ビット分は、包含するJANコードを記述します。65ビット目から128ビット目までは、例えば、製品一つ一つの製造番号を記述できます。この例では、64ビットを製造番号に使えるので、264個の製品に、それぞれ異なる製造番号を振ることができます。
JANコードのほかにも、出版物に割り当てられるISBN(International Standard Book Number)、グローバルIPアドレス、電話番号などを包含できるほか、工夫しだいで、ほとんどのコード体系を包含できると思われます。
※ucodeの応用例については、T-Engineフォーラムについて紹介する回の中で詳しく紹介する予定です。
【3】ISO/IEC 15963
ISO/IEC 15963は、ISO化されたRFIDのための唯一のID体系です。長さは64ビットで、先頭の8ビットに発行機関を識別する「割り当てクラス」、続く8ビットは、割り当てクラスが「11100000」の場合、RFIDタグを製造するメーカーのID、そして残り48ビットがシリアル番号になっています 。EPCやucodeと比較すると、十分な桁数が用意されているとは言い難いですが、用途によっては十分であるとも考えられます。
RFID普及を目指し、ITU-Tで始まった標準化作業
第1回目でも書きましたが、RFIDを普及させるにあたって、前述のID体系の違いは早急に解決しなければならない課題です。そこで、このような問題を解決するため、2005年からITU-Tで標準化に向けた活動が開始されました。
ITU-Tでは、EPCglobalやT-Engineフォーラムのシステムのように、ネットワークを利用するRFIDシステムを、「Networked-RFID」(現在はこれを略して「N-ID」と呼称することになった)と名付け、RFIDシステムのネットワークに関する部分の標準化を行い、ISOと連携してRFID全体の標準化を進める意向です。ネットワーク部分の標準化にあたっては、IDが重要な課題であり、ID体系の統一に重点が置かれることが予想されます。
※この標準化の動きに関しては、Auto-ID LabやユビキタスIDセンターの紹介をする回の中で再度触れる予定です。
コラム
周波数やプロトコルをソフトウェアで変更できるRFIDリーダー/ライター
FlexReaderWriter
NECシステムテクノロジー株式会社が2006年6月に発表、販売開始した「FlexReaderWriter」は、ソフトウェアを変更することで、異なる周波数や異なるプロトコルに対応できるようになります。これにより、すでに使用しているRFIDリーダー/ライターそのものを交換することなく、異なるRFIDタグや仕様などに対応することができます。
FlexReaderWriterは、RFIDリーダー/ライターと、RFIDリーダー/ライターを管理するためのサーバー用集中管理ソフトウェアから構成されています。RFIDリーダー/ライター本体には、現在のところ、13.56MHz帯と2.45GHz帯のアンテナや無線回路、FPGA(Field Programmable Gate Array、プログラミングできる半導体チップ)やDSP(Digital Signal Processor、音声・画像などのデジタル信号を処理するための半導体チップ)によるソフトウェア無線処理回路、各種のプロトコル・プログラムなどが内蔵され、RFIDタグを読み書きしたデータを無線LAN経由で受け渡しします。
また、サーバー用集中管理ソフトウェアからの更新ソフトウェアを受け取ることもできるため、複数のRFIDリーダー/ライターが設置してあるそれぞれの場所まで足を運ぶ必要もなく、サーバー側から指示するだけで、各RFIDリーダー/ライターのソフトウェアを更新できます。
▽FlexReaderWriterプレス・リリース
http://www.necst.co.jp/press/20060628/index.htm (NECシステムテクノロジー)
用語解説
JAN:Japan Article Number
国際EAN(European Article Number)協会(当時、現在は規模拡大に伴い、GS1:Global Standard Oneに名称が変更された)によって割り当てられた国番号(45または49)、5桁の企業コード、5桁の品目コード、1桁のチェック・デジット(誤読防止のための検査数字)の合計13桁の数字で構成される商品コード。 ヨーロッパ、アジア、オセアニアで使用されているものがEANで、JANはJIS化された日本での呼称。
このJANコードをバーで表したものがおなじみのバーコード。スーパーやコンビニエンスストアなどでは、商品に付けられたバーコード(JANコード)を読み取ることで、その商品の品名や価格を判別する。JANの場合には、合計8桁の短縮バージョンも用意されている。