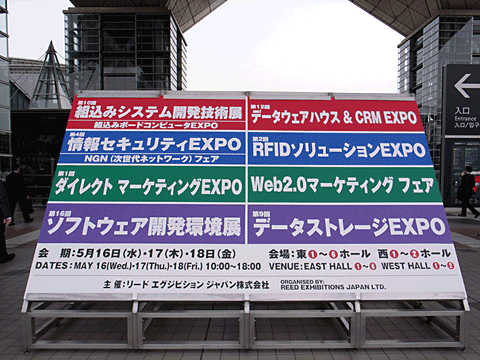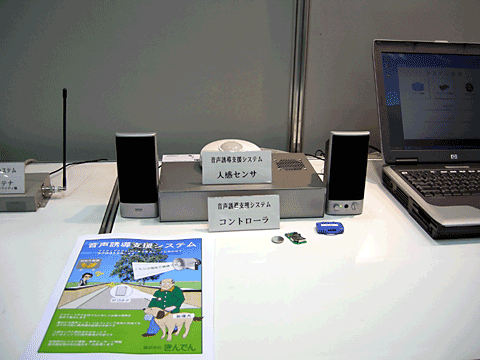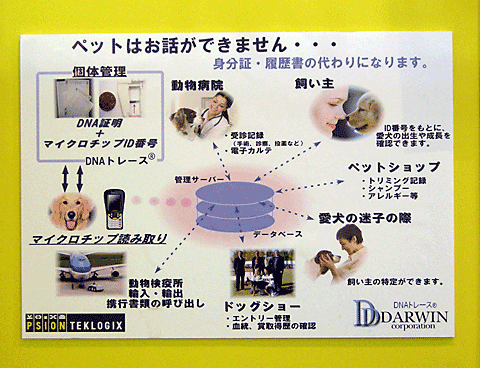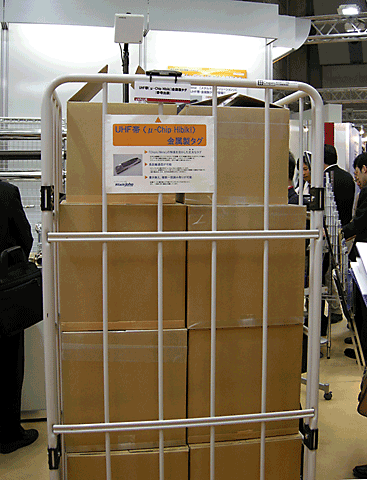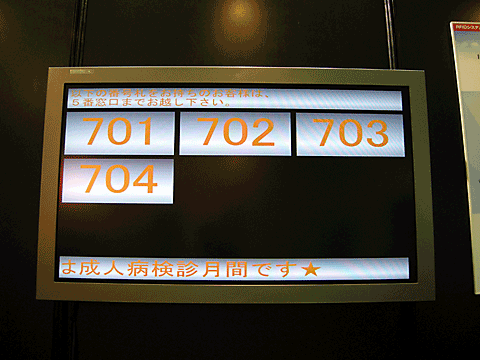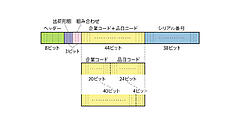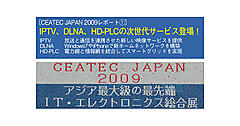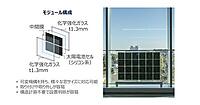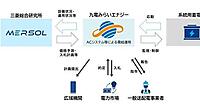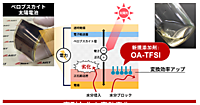RFIDの基礎と最新動向(番外編4):RFIDソリューションEXPO(RIDEX)レポート
2007年5月31日 (木曜) 0:00
本連載「RFIDの基礎と最新動向」では、2006年から各種産業分野で本格的な運用事例が目立ちはじめたRFIDの基礎から応用例、最新動向までを取り扱います。今回は、番外編として、2007年5月16日~18日に開催された第2回 RFIDソリューションEXPOを取り上げます。
出展社は2006年の約2倍
RFIDソリューションEXPO(略称:RIDEX)は、見本市の主催を専門に行っているリード エグジビション ジャパンが主催する、RFIDを活用したソリューション、RFIDシステム構築に必要な製品やサービスを集めた展示会です。2006年6月に第1回が開催され、今回の開催が第2回となります。第1回の出展社数は68社、今回の出展社数は125社と約2倍に拡大しています。
今回は、RFIDソリューションEXPOのほかに、第16回 ソフトウェア開発環境展(SODEC)、第12回 データウェアハウス&CRM EXPO(D&C)、第10回 組込みシステム開発技術展(ESEC)、第9回 データストレージEXPO(DSE)、第4回 情報セキュリティEXPO(IST)、第1回 ダイレクトマーケティングEXPO(DME)、Web2.0マーケティング フェアの合計8種類の展示会が同時に開催されました。
これらの展示会は、すべてIT関連というだけではなく、それぞれ関連していることもあります。例えば、RFIDソリューションEXPOは、組込み開発技術展からRFID関連の展示が独立したものです。このためRFIDソリューションEXPOとして独立した今でも、出展者の意向によってはRFIDに関連する展示が組込み開発技術展で行われていることがあり、展示会へ行った際には、同時開催されている展示会も見ておくことをお勧めします。
それでは同展のなかで要注目の製品やサービスをピックアップして紹介します。
MMチップを利用したICペーパー
MMチップとは、トッパン・フォームスなどが開発を進めているRFIDタグです。ICチップ上に微小アンテナが形成され(チップオンアンテナ)、UHF帯や2.45GHz帯で使用する場合には、チップ単体で使用できます。また、マルチバンドに対応しており、外部アンテナを使用することで13.56MHz、UHF帯(868MHz帯、915MHz帯、950MHz帯)、2.45GHz帯の3バンドで利用できます。チップの寸法は0.7mm四方、厚みは0.07mmで紙などに漉き込むことが可能です。
MMチップ自体は、RFID関連の展示会などで2004年頃から目にしていましたが、その後は目立った動きが見えませんでした。しかし、今回の展示会ではMMチップをスレッドテープにあらかじめ埋め込んでおいて、そのスレッドテープをICペーパーに漉き込むことで、RFIDタグを埋め込んだICペーパーが製品例として出展されました。
ICペーパーを書類、証書、伝票、金券などに使用することで、真贋を判定できるようになります。対応可能な周波数帯は、チップオンアンテナとなるためUHF帯か2.45GHz帯で、通信距離はリーダー/ライターと接触させるか数mm程度になります。通信距離の短さは、意図しない読み取りを防ぐのにプラスに働きます。価格は、A4判の大きさで、1枚あたり20~30円を予定し、2007年の販売開始を予定しているということです。
ちなみに、ICペーパーの開発にあたって協力している王子特殊製紙は、MMチップを使用したICペーパーだけでなく、ミューチップの漉き込み(愛・地球博の入場券で使用されました)も担当しており、現在のところ同社だけがRFIDタグの漉き込みの実績を持っている状況です。
アクティブタグを利用した音声誘導支援システム
初出展のきんでんからは、音声誘導支援システムが出展されました。このシステムは、アクティブ型RFIDタグと人感センサー、音声案内用スピーカーなどを組み合わせて、視覚障害者などを音声で案内しようというものです。例えば、男性の視覚障害者にアクティブ型RFIDタグを渡し、男性という属性をあらかじめ登録しておきます。これにより、トイレの前に設置してある人感センサーが人の接近を認識すると、RFIDタグから発信されているIDに基づいて性別が判断され、男性なら「右です」、女性なら「左です」というように音声による案内が流れます。属性を性別でなく国籍にすれば、日本語と英語の案内を使い分けることも可能です。また、RFIDタグだけ、あるいは人感センサーだけで音声案内を流すことも可能です。このほか、時間帯で音声案内の内容を変えることも可能です。このシステムは、7月にオープンする関西の公共施設に導入され、視覚障害者のために利用される予定です。
利用者の属性に応じて案内を変えるという考え方は、自律移動支援プロジェクトと共通します。しかし、自律移動支援プロジェクトは、非常に大きな構想で、実現には多くの費用と時間が必要ですが、音声誘導支援システムは非常に手軽でありつつも、限定的なエリアでの利用には必要にして十分な機能を備えていると言えるでしょう。特に、自律移動支援プロジェクトでは、案内サービスを提供するのに現在のところ高価な専用端末を貸し出す必要がありますが、音声誘導支援システムならアクティブ型RFIDタグなので、高くても2,000円程度と安価です。もちろん、機能はまったく異なりますが、この価格差は、初期投資や運用管理の点で有利です。
未病予兆検出サービス
ケータイ向けコンテンツの配信などを行っているテルヤも初出展した。富士通、スター精密との共同で、病気の予兆を検出したり、入院患者の動静を検出したりといった機能を実現する未病予兆検出サービスを展示しました。これは、スター精密の開発した「1軸動電型振動センサー」とISO 18000-6 type Bに準拠したRFIDタグチップを利用した、内蔵電源を必要としないセンサータグを開発し、そのセンサータグを取り付けた人(患者など)の姿勢(起きている、座っている、寝ている、さらには横を向いて寝ているときには、右側が下、あるいは左側が下など)をモニタリングします。さらに、将来的には、体温の変化などをモニタリングすることも検討されています。
また、センサータグを人以外に取り付けて、品質管理や異状の発見に利用するセンシングネットワークサービスも計画されています。具体的には、輸送中の貨物にセンタータグを取り付けて振動や温度をモニタリングして貨物の品質保全を行う、線路にセンサータグを取り付けて振動やひずみをモニタリングして土壌崩落の予兆検出を行う、建造物にセンサータグを取り付けて振動やひずみをモニタリングして建造物の異状発見を行うといった例が挙げられています。
RFIDによるペットのDNAトレース
ペットや家畜の体内にRFIDタグを埋め込み個体管理に役立てるということは、すでに行われています。サイオン・テクロジックスとダーウィンが共同出展したDNAトレースシステムは、RFIDタグによる個体管理にDNA証明を組み合わせて、RFIDタグを身分証や履歴書の代わりに使用しようというシステムです。
犬の場合には、首の背中側あたりにRFIDタグを埋め込み、そのRFIDタグをRFIDリーダーで読み取り、読み取ったIDをもとに管理サーバーのデータベースに問い合わせることで、受診記録、電子カルテ、アレルギー情報、血統証、賞取得歴、検疫書類、飼い主情報などを呼び出すことができます。これにより、犬の個体情報を一元管理することが可能になります。
UHF帯金属製RFIDタグ
日立情報システムズからは、UHF帯に対応した金属製RFIDタグが出展されました。これは、すでに同社から発売されているChipin/Metal(2.45GHz帯に対応した金属製RFIDタグ)のUHF帯モデルで、響タグを採用することで、通信距離を2m程度まで伸ばしています。
外装にステンレスを採用し、金槌で叩いても壊れない強度を確保しているほか、劣化や錆の心配がなく、耐久性、耐候性にすぐれています。また、RFIDタグの両端にあるネジ穴を利用して、対象物にネジ止め、リベット止めすることで、脱落を防ぎます。具体的な用途としては、写真7のようにカゴ台車に取り付けて入出荷検品に使用したり、工具や機器、金型、資材などの管理に使用したりすることが考えられます。8月に予定されている新型ミューチップの登場を待ってから、10月頃にリリース予定とのことです。
Chipin/Show
日立情報システムズからは、RFIDを利用したコンテンツビューアも出展されました。これは、RFIDリーダーにかざしたRFIDタグに対応したコンテンツ(静止画、動画、スライドショー)が表示されるというシステムで、店舗やアミューズメント施設、企業の受付、ショールーム、博物館などでの利用を想定しています。例えば、商品にRFIDタグを取り付けておけば、RFIDリーダーにかざした商品についてのコンテンツが表示されます。あるいは、説明カードにRFIDタグを取り付けてば、その説明カードに書かれている内容に関連するコンテンツが表示されます。さらにオプション機能を追加すれば、RFIDタグの読み取り回数による人気ランキング、選択形式によるアンケート、複数のRFIDタグを組み合わせて読み取ることによる組み合わせ情報の表示、在庫情報管理システムとの連携といったことが行えます。
窓口番号呼出システム
役所や病院の精算窓口などで、番号札と証明書やカルテの入った書類ケースをマッチさせるために、番号札と書類ケースにバーコードを貼って管理するシステムが導入されていることがあります。ソランの窓口番号呼出システムは、バーコードの代わりにRFIDを使用したものです。RFIDを使用するメリットは、番号札や書類ケースのRFIDタグを読み取るに際に角度や向きを気にせずに済むという点の他に、もう一つ大きなメリットがあります。それは、バーコードリーダーに比べてRFIDリーダーの方が低価格なことと、バーコードラベルよりもRFIDタグの方が使用可能期間も長いのでトータルコストを抑えることができるということです。RFIDは「バーコードよりも高価」だと一般的に思われているかもしれませんが、RFIDタグを長期間にわたって再利用するようなケースでは、トータルのコストが抑えられることがあります。この窓口番号呼出システムは、実際に2006年から札幌市西区区役所に導入されています。
重ねた書類に対応するファイリングセキュリティシステム
サトーからは、RFIDを利用した重要書類管理システムが出展されました。書類フォルダーなどにRFIDタグを取り付け、アンテナを内蔵した書棚で書類の取り出しなどを管理するシステムは、すでに数多くの製品があります。しかし、このシステムでは、RFIDタグを最大50枚まで重ねた状態でも読み取ることができる「積層ICタグ」を採用することで、大量の書類を密集して保管してある状態でも、確実な読み取りが可能となっています。ちなみに、RFIDタグ50枚を約4秒で読み取り可能です。
ファイリングセキュリティシステムで使用されている「積層ICタグ」は、日本発条の製品で、85.0mm×54.0mm×0.9mmのカード形状となっています。内蔵するICチップには、13.56MHz帯を使用するISO/IEC15693に準拠したTag-it(テキサスインスツルメンツ)、I-CODE SLI(フィリップス)などが利用可能なので、ISO/IEC15693に対応した市販のRFIDリーダーが使用できます。
■■■