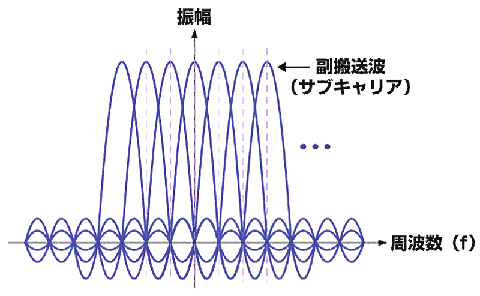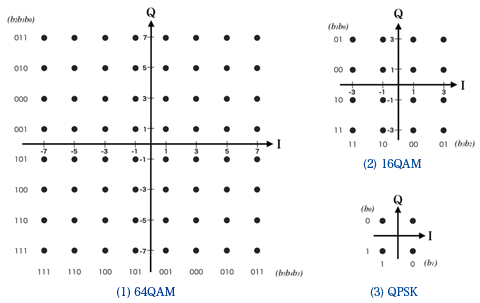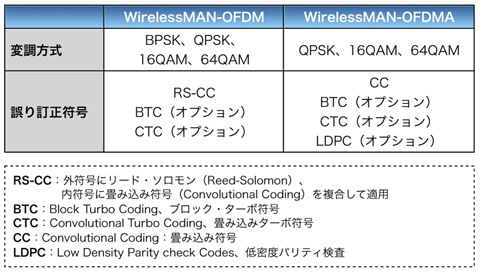OFDMとOFDMA技術
WiMAXフォーラムでは、固定WiMAXのPHYにOFDM方式を、モバイルWiMAXのPHYにOFDMA方式を採用したことは先に述べたが、OFDM技術は互いに直交(隣接する副搬送波の中心周波数で振幅成分が“ゼロ”となる周波数を組合せて相互干渉が生じない)関係の副搬送波(サブキャリア)を周波数軸上に配列して、高速なデータを副搬送波に並列分配して伝送する技術である。
現在は、地上デジタル放送や無線LAN(IEEE802.11g/a)などにも採用されている。OFDM技術は、サブキャリアで伝送する情報のシンボル長が長く、サブキャリアあたりの伝送帯域幅が狭く遅延分散の影響を受けにくいこと、情報シンボルの一部をコピーしてシンボルの先頭に付加するGI(Guard Interval、ガード・インターバル)の手法によって、電波の伝搬路で発生するマルチパスによる符号間干渉を簡易な仕組みで除去することが可能なことなど、フェージングに対する耐性が高い特徴を持つ。OFDM技術は、今後ブロードバンド化する無線データ通信の領域で主流となる技術であると目されている(図1)。
各サブキャリアは、受信側のCINR(搬送波レベル対干渉・雑音比)に応じて、電波状態が良い(CINRが高い)場合には、64QAM変調や、16QAM変調などの多値変調を適用して効率的なデータ送信を行う。一方、電波状態が悪い(CINRが低い)場合にはQPSK変調方式を適用して、伝送レートは低下するものの確実に受信者にデータを伝送することを可能とする適用変調(AMC:Adaptive Modulation and Coding)を採用する。図2に各変調方式のビットマップ(ビット配置)を示す。
ビット誤り訂正(FEC:Forward Error Correction)には、CC(Convolutional Coding:畳み込み符号)、CTC(Convolutional Turbo Coding:畳み込みターボ符号)、BTC(Block Turbo Coding:ブロック・ターボ符号)のほか、LDPC(Low Density Parity check Codes:低密度パリティ・チェック符号)などが規定される(表2)。
WiMAXフォーラムでは現在、複信方式として、送受信に同一周波数を用いて送受信の分離は時間分割で行うTDD(Time Division Duplex、時分割複信)方式を中心に検討が進められているが、送受信に異なる周波数を用いるFDD (Frequency Division Duplex、周波数分割複信) 方式も、IEEE802.16e-2005で標準化されている。
TDD方式を採用したシステムの特徴は、送受信に割り当てる時間を変えることによって、上り/下りのデータ伝送速度を最適値に設定できる(ただし、運用中の動的な変更は対象外)ことである。
このため、IPデータ通信を用いるブロードバンド・アクセスに多く見られるような、送受信が非対称なデータ・トラフィックに親和性が高いシステム構築が可能となる。また、日本のように都市部で周波数が切迫して、送受信ペアバンド(送信と受信に異なる1対の周波数帯を使用する方式)の確保が困難な状況においても、単一バンドの周波数で対応できるため、比較的柔軟に周波数の割り当てが可能となる。
さらに、送受信に同一の周波数を用いるため、受信信号による伝搬路の推定が比較的容易で、アダプティブ・アンテナなどの無線通信の高度化技術への親和性が高く、広帯域の無線通信に有利な方式であると考えられる。