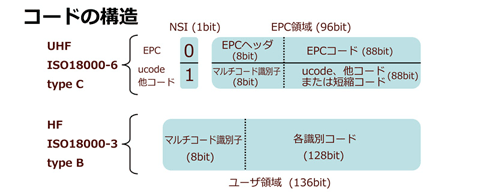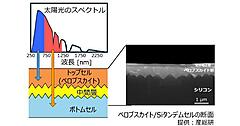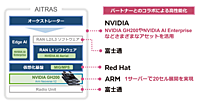RFIDの基礎と最新動向(10):「マルチコード相互運用プロジェクト」
2007年4月25日 (水曜) 0:00
本連載「RFIDの基礎と最新動向」では、2006年から各種産業分野で本格的な運用事例が目立ちはじめたRFIDの基礎から応用例、最新動向までを取り扱います。第10回目は、異なる3種類のコード体系が記録されたRFIDタグを、混在して利用できるプラットフォームの実証実験プロジェクトをレポートします。
複数コードの混在運用を目指した経産省の実証実験
このプロジェクトは、経済産業省 「平成18年度エネルギー使用合理化電子タグシステム開発調査事業」(電子タグ実証実験事業)のテーマ2「マルチコード相互運用プロジェクト」として、Auto-IDラボ・ジャパン、ユビキタスIDセンター、日本ユニシスの3者により行われました。
経済産業省の公募資料によれば、「マルチコード相互運用プロジェクト」の目的と事業内容は、次のとおりです。
1. 事業の目的
IT戦略本部において平成18年1月に「IT新改革戦略」が取りまとめられた。電子タグは今後のIT戦略を推進する上での重要な施策の一つに位置付けられており、IT経営の確立、環境配慮型社会、安全・安心な社会の実現等の多岐にわたる分野での利活用が求められている。
特に電子タグは、製品ライフサイクルにわたるシームレスな企業間連携を加速化し、製造段階から流通、販売、リサイクル等に至るサプライチェーン全体の最適化を実現するものとして期待されている。
そこで本事業では、運用と技術の相互補完による高信頼システムを実現し、国際的な電子タグシステムの更なる普及を推し進めるため、国際標準化の積極的な推進、国内独自規格と国際標準規格の整合を狙いに2つのテーマを設定し、広く業界・企業等から提案を募集し実証実験を実施するものである。
これにより、製品ライフサイクル全体にわたる電子タグの利活用を加速化し、サプライチェーン全体の最適化等を通じた我が国のエネルギー使用合理化に資することを目的とする。
2. 事業内容
実証実験事業についてテーマを二つ設定し、それぞれ以下の事業を実施する。
テーマ1:国際標準実現型プロジェクト
ISO国際標準に準拠した電子タグ共通基盤の構築を行い、に資する。
- 電子タグ関係国際標準化会議参加国とのメリット共有による提案規格の協調的推進
- 国際市場における電子タグシステムの有用性確認
- ユーザー/ベンダーメリットの導出による電子タグ普及促進
- 貿易手続きの簡素化検討
テーマ2:マルチコード相互運用プロジェクト
ISOコード体系とuコード体系といった異なるコード体系が混在する環境において、コードの相互運用に必要となるプラットフォーム(コードの違いを吸収し情報流通を確保する電子タグシステム)を開発し、実フィールドにおける実証を行い、運用が可能なことを証明することで、に資する。
- 異なるコード体系の混在が電子タグ導入の阻害要因になることの回避
- 個体識別子に関する将来の技術動向の変化に対する産業界、利活用者の不安払拭
また、公募資料には、応募の要件として次の内容が提示されています。
<テーマ2>マルチコード相互運用プロジェクト
- 異なったコード体系に基づいたシステムを採用している機関間において、システム間がシームレスにつながる情報プラットフォームを設計・構築し、相互運用性の検証を行うこと。
- 電子タグに格納されるコードの管理や研究・開発を自ら行っている機関が参画し、実証実験に取り組むこと。
- 実際の現場においてヒトやモノの動きを把握する等、実運用における検証を行うこと。
- 本事業で開発する情報システムのインタフェースを公開し、他の事業者も利用することができるものであること。
この要件では、具体的な組織名が示されていませんが、「電子タグに格納されるコードの管理や研究・開発を自ら行っている機関」とは、Auto-IDラボとユビキタスIDセンター以外には考えられないでしょう。
このほか、日本ユニシスのプレスリリースには、プロジェクトの目的などとして、次のような内容が挙げられています。
電子タグの実証実験は数多く実施されていますが、本格的な導入に慎重な要因のひとつに、コード体系が複数あることへの不安が挙げられます。
今回、委託対象事業に採択されたプロジェクトは、アプリケーション側が「ucode」と「EPC」という2つのコード体系や「社内独自コード」などの違いを気にすることなくシステムの運用が出来る環境-プラットフォーム-の開発とその有効性の検証を目的としています。
実利用のシーンでは、以下のようなことが想定されます。
- 倉庫でのピッキングや出荷検品の際に、納品元、出荷先によってコード体系が違う場合に、コード体系の違いをプラットフォームで吸収させ、業務処理プログラムはシンプルに構築できるようになります。
- 納品元も納入先の要求に合わせて、さまざまなコード体系の使い分けが不要となります。
異なる3種類のコード体系を混在させて運用
マルチコード相互運用とは、ハードウェアレベルでは同じRFIDタグに異なるコード体系を記録した状態で混在して、Auto-IDラボとユビキタスIDセンターの、それぞれのプラットフォームで運用することです。RFIDの利用が拡大することを考えた場合、複数のコード体系が混在する状況は避けられませんし、混在を許容できなければRFIDの利用拡大は考えられないというのが多くの関係者の意見です。
今回のプロジェクトでは、Auto-IDラボ(EPCglobal)のEPC(Electronic Product Code)、ユビキタスIDセンターのucode、そして独自コードの3種類を混在させて実証実験を行いました。
コード(ID)体系を混在させて運用するにあたって第一の課題と考えられるのが、コードの長さの違いです。EPCは96ビット、ucodeは128ビットが基本です。さらに、EPCはバーコードから発展した体系となっていて、企業を表す部分、品目を表す部分など、コードに意味があります。一方、ucodeはコードに意味がありません。
異なるコード体系を混在させて運用する場合の解決方法として、1つのリーダーで複数のコード体系に対応できるようにして、リーダー/ライターでRFIDタグのコードを読み取ったあとに、コード体系を判別し、以降の処理方法を振り分けるという方法が考えられます。一方、リーダー/ライターを共用することを諦めて、コード体系の数だけ専用のリーダー/ライターを用意するという方法も考えられますが、将来的にコード体系が増えた場合の対応が大変ですし(設置するリーダー/ライターの数が大きく増えてしまう可能性が十分に考えられます)、スマートな解決方法とは言い難いでしょう。
今回のプロジェクトでは、RFIDタグに記録されているコードの先頭に、使用しているコード体系を識別するヘッダーを追加し(図1)、RFIDタグを読み取った時点で、識別したコード体系に基づいて処理を振り分ける方法を採用しています。具体的には、8ビットのマルチコード識別子(Multi-code Indicator)をコードの冒頭部分に置き、その内容から、続くコードがEPCなのか、ucodeなのか、あるいはその他のコード(独自コード)なのかを判定し、処理を振り分けています。このため、1種類のリーダー/ライターで複数のコード体系に対応できます。また、EPCには、NSIと呼ばれる1ビットのエリアがあり、その値が「0」ならEPC、「1」ならEPC以外という判定を行います。
公開イベントでの実証実験は成功
実証実験は、2006年11月22日と23日に、東京・丸の内の丸ビル、三菱ビル、東京ビルTOKIAで開催された、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の研究成果発表を行う「SFC Open Research Forum 2006」(1回目)と、2006年12月5日から7日に東京国際フォーラムで開催された「TRONSHOW2007」(2回目)の2つのイベントで行われました。
SFC Open Research Forum 2006で行われた1回目の実証実験では、UHF帯を使用するRFIDタグ(ISO/IEC18000-6 type C、いわゆるGen2)が6,000枚用意され、公開実験への参加を希望する来場者に配布されました。6,000枚のうち、5,500枚にはEPC、400枚にはucode、100枚には独自コードが記録されました。
公開実験に参加した来場者は、会場内の10カ所に設けられたリーダーにRFIDタグをかざすと移動したことが認識され、エリア別に業種ごとの人数がディスプレイに表示されます。混雑状況の確認にもなりますが、会場を倉庫に置き換え、来場者を部材に置き換えると、倉庫内で、部材の種別ごとに所在と移動の状況を把握するためのアプリケーションと考えることができます。
また、あらかじめ携帯電話のメールアドレスを登録しておくと、会場内に設けられたゲートを通過するごとに、そのエリアの情報が携帯電話のメールアドレスに送信されます。ただし、1度送信されたエリア情報が再度送信されることはありません。
実証実験に関するセッションでは、Auto-IDラボ・ジャパンの中村修副所長から、混在運用による問題は発生していないとの報告がありました。
TRONSHOW2007で行われた2回目の実証実験では、13.56MHz帯を使用するRFIDタグ(ISO/IEC18000-3 type B)が入場証(写真1)として配布されました。ただし、実証実験に参加するには事前登録が必要で、事前登録をしない限りは、入場証としての役割しか果たしません。
運用されたアプリケーションは、1回目の実証実験とほぼ同じですが、13.56MHz帯を使用するRFIDタグのため、通信可能距離がUHF帯より短く、携帯電話への情報送信は、展示会場内に設置されたリーダー(写真2)にRFIDタグをかざさないと行われないようになっていました。
TRONSHOW2007での実証実験でも、マルチコードで問題なく運用できていることが、セッションで発表されました。
ただし、この実験のシステムは、ucodeの立場から見ると冗長な処理を行っている点があります。それは、ucode自体は、もともと他のコードを内包できる仕組みになっており、バーコードで使用されているJANコードやEPCを、そのまま取り込むことが可能となっています(この仕組みについては、本連載の第3回で解説しています)。しかし、今回の実証実験では、ucodeの前にさらにヘッダーを付け加えており、屋上屋を架すことになっています。それ以外の問題として、RFIDタグによってはヘッダーを書き込めるエリアがないものもあり、ユーザーが自由に利用できるユーザーメモリ領域にヘッダーを書き込まなければならない場合もあります。
これらの細かい課題について、プロジェクトの報告書でどのように扱われているのか興味があるところですが、本稿の執筆時点で報告書が公開されていないので、公開されたタイミングで再度取り上げたいと思います。
マルチコードからマルチプロトコルへの発展
マルチコードをさらに発展させて、マルチプロトコル、つまり1台のリーダー/ライターで複数の周波数のRFIDタグに対応するということが考えられます。
マルチプロトコルのリーダー/ライターを実現するための技術の1つとして、ソフトウェア無線があります。これは、電波の処理を行う回路をソフトウェアで作り、必要に応じて回路をソフトウェアにより変更しようというもので、NECシステムテクノロジーのFlexReaderWriterといった製品も登場しています。一方で、コストの面から、小型化された(ハードウェアの)無線回路を複数組み込んだ方が安上がりだという意見もあります。
しかし、いずれの方法を採用するにしても、マルチプロトコル対応リーダー/ライターの実現性には疑問の余地はありません。マルチコードの課題が解決されれば、マルチコード対応で、マルチプロトコル対応のリーダー/ライターが登場することでしょう。
そして、その頃にはリーダー/ライターの低価格が進み、RFIDの導入に拍車がかかるようになるかもしれません。
■■■