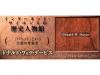人間の知的能力の増強
エンゲルバートはこの会議の直後に「人間の効率に関する計画」を執筆し、バネバー・ブッシュに「われわれが思考するごとく」の引用許諾を求める5月25日付けの手紙を添えて送付した。かれは62年10月に「人間の知的能力の増強:概念フレームワーク」を、空軍科学研究局情報科学部長宛の報告書として提出し、10月に国防省高等研究計画局(ARPA)の情報処理技術担当者になったリクライダーにも研究助成を求める提案書とともに送付した。この論文はその後も書き換えられ、63年に出版された論文集「情報処理展望」に「人間の知的能力を増強するための概念フレームワーク」の表題で収録された。
エンゲルバートは、人類が直面する問題がますます複雑化するため、理解し難くなる状況を速に克服して解答に到達する方法を、デジタル技術で実現する必要性を説いた。かれが意図した知性の増強は、解決すべき複雑な問題に対処可能なレベルに知性を引き上げることで、機械が人間の代わりに働くオートメーションや機械のみが思考作業を行う人工知能とは異なっている。
かれは、人と道具が相互作用するシステム全体の能力が、構成要素の組合せにより変化することに注意を向けた。人と道具はシステムの物理的要素であり、相互作用を成立させるための言語と方法論があり訓練により能力に差がでる。
道具がペンと紙であれば、人は訓練された手指と筋力の加減で文章を書き図を描く。道具がタイプライタなら、訓練により記述速度が向上するが、入力ミスが発生しやすく図は描けない。道具がディスプレイとキーボードを備えたコンピュータでコピー、カット、ペーストが可能なら、入力ミスによる時間損失は最小化され、図と記号のライブラリや辞書を電子的に提供することができる。
エンゲルバートは、タイプライタがコンピュータによりワープロに変容して獲得した能力が、数多くの人の仕事効率を高め、さらに情報検索や通信能力を付加することにより、人は従来より格段に広い知識を駆使して深い思考に到達できると考えた。人と道具の関係の変化は、言語と方法論と訓練を変化させ、組織の能力を増強し、外部にも波及する。エンゲルバートの知的能力の増強(augmentation)は、数多くの人々の仕事の内容に変化を与え問題解決能力を高め続ける共進化プロセスになっている。
マウスの発明
エンゲルバートは62年にライトペンと異なり、手を離してもその場にとどまる画面指示装置として、グローブか指キャップを利用する方法を検討していた。かれは63年11月にネバダ州リノで開催されたグラフィクスの学会に出席して、11月14日に積分器を使ってXY座標上の停止点からの移動距離を測る方法をノートに書き留めた。
エンゲルバートはこのアイデアをNASAに提案し、当時研究助成を担当していたロバート・テイラーを通じて64年に85,000ドルの研究資金を獲得した。64年7月にサザランドがARPAの情報処理技術部長に就任すると、テイラーがその助手となり、65年に初回100万ドルおよび年50万ドルがエンゲルバートにタイムシェアリング・システムの研究費として支給された。
エンゲルバートはCDCのミニコンCDC160Aを購入し、自分の研究グループをARC(Augmentation Research Center)の名で発足させた。ビル・イングリッシュが主任技師となり、エンゲルバートが「バグ」と呼んでいた装置を開発することになった。
最初のマウスは縦方向と横方向に机上を回転する2つの円盤を内蔵し、円盤の中心軸は回転を電圧に変換するポテンショメータに連結されてXT座標の位置を判別し、A/D変換器によりコンピュータに位置情報を伝える仕組みだった。この装置はXYポジション・インジケータと呼ばれ、ボタンが1つでケーブルは手首側からでていた。
エンゲルバートとイングリッシュは65年7月に、NASAラングレー研究所に報告書「コンピュータ支援によるディスプレイ制御」を提出した。エンゲルバートは5つのボタンを望んでいたが、イングリッシュは何度も改良を重ね物理的制約からボタンの数を3つにした。エンゲルバートは「コードキーセット」と呼ばれる左手で命令や文字を入力する装置も開発した。コードキーセットは、ピアノの鍵盤のように長めのキーを5つ備え、5本の指を乗せて使いキーの組合せで31文字を表現できた。
NLSとタイムシェアリング・システム
エンゲルバートは63年に、コンピュータ・ネットワークと知的能力の増強を融合させるNLS(oN Line System)の論文を執筆し、CRTディスプレイ、キーボード、マウス、コードキーセットを利用するテキスト編集システムの開発を始めた。かれは、これらの装置とソフトウェアで可能になったことを映像に記録し、65年5月にMITで開催されたARPA支援の研究者の会議で披露した。テイラーは対話型編集システムの価値を認め、タイムシェアリング・システムで利用できるようにする提案書を提出するように促した。
ARCではイングリッシュ、ロジャー・ベイツがハードウェア、デイブ・ホッパーがソフトウェアの開発を担当していた。66年に入ると、ミズーリ州のワシントン大学からジェフ・ルリフソンやドン・アンドリュースがARCの研究スタッフに加わり、エンゲルバートはCDC3100を新たに導入して開発体制を強化した。
66年7月にテイラーがARPAの情報処理技術部長になり、12月にローレンス・ロバーツがチーフサイエンティストに就任して、ARPANETのプロジェクトが実現に向けて動き始めた。ロバーツは67年4月にミシガン州アナバーでARPANETの検討会を開催し、エンゲルバートはネットワーク・コミュニティのサポートサービスを担当するネットワーク・インフォメーション・センタ(NIC)の開設と運営を行うことを申し出た。
エンゲルバートは67年7月に、ARPAから565,500ドルの新規助成を得で、SDS940を導入した。このコンピュータは、UCBでARPA支援によりSDS930にページング方式の仮想記憶を導入してタイムシェアリングに対応させていた。この仮想記憶は、1つのファイルを複数のユーザが共有して表示と入力が可能で、グループで編集作業を行うことができた。
エンゲルバートはSDS940を12人で同時に使用しようとしたが、描画が可能なベクターディスプレイは1台20,000ドルと高価で、テレビと同じラスタースキャンディスプレイも大量のメモリを搭載する必要があった。かれは1台5,500ドルの5インチのベクターディスプレイを12台購入し、2台のディスプレイ・ジェネレータを介してSDS940のメモリバスに接続した。かれは12台のモノクロビデオカメラと17インチのテレビ用CRTを購入して、5インチの画面を17インチに拡大しキーボード、マウス、コードキーセットで操作できるようにした。