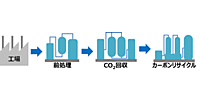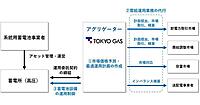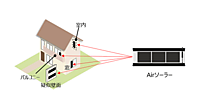≪3≫シャノンの定理と実効速度
≪3≫シャノンの定理と実効速度
■ シャノンの定理とは。
近 シャノンの定理とは、若干、数式が入ってわかりにくいかもしれませんが、図4に示すように、ワイヤレス環境における実効速度(C)は、通信で使う周波数の帯域幅(W)と、S/N(信号と雑音の比)のlog(ログ)の掛け算、すなわちC=W×log2(1+S/N)というふうに定義されています。そうすると、この式から、電波の帯域幅(W)をたくさんもらえば、もらうほど高速になるのです。携帯電話は、最初アナログの頃はキャリアの帯域幅(W)は10kHz程度でした。それが、デジタルになって数十kHzから数百kHzとなりました。さらにCDMAになって数MHzになりました(<例>W-CDMAの場合:上りと下り各5MHz幅)。さらにOFDMになって数十MHzになった(<例>LTEの場合:上りと下り各20MHz幅)。その幅の広さ(W)が速度と基本的には比例関係になっているのです。
■ なるほど、わかりやすいですね。
近 ですから、使用する周波数帯域幅をどんどん広帯域化して、高速化してきたというのがこのワイヤレスの世界の歴史なのです。
しかし、1人当たりの伝送速度は確かにこのように速くなりますが、ユーザー全員が使える容量というは割り当てられた帯域幅しかないわけです。昔は10kHz程度の帯域幅で1人がしゃべり(使用し)、同時に何百人、何千人としゃべれたのはそれだけ帯域幅があったのです。ところが、携帯の事業者への帯域幅(W)の割り当ては、その後数倍程度しか増えていないのです。しかし映像配信などが急増したりして1人当たりが使う帯域幅はどんどん増えてきました。それでも通信できるのは、みんながみんな同時にしゃべるわけではないので、瞬間的には各自が1人独占のような形になって利用できているのです。
関連記事

ウィルコムの次世代PHS(XGP)戦略を聞く(3):次世代PHS(XGP)の6つのコンセプト
2008年10月10日 0:00

ウィルコムの次世代PHS(XGP)戦略を聞く(4):次世代PHS(XGP)のロードマップ
2008年10月21日 0:00

対談:電波・周波数を語る(1):通信に適した周波数はなぜ5GHz以下なのか?
2006年11月6日 0:00

WiMAXからLTE、次世代PHSまで、次世代無線ネットワークが勢ぞろい =ワイヤレスジャパン2008=
2008年8月11日 0:00

真のモバイル・ブロードバンド時代を実現するUQ WiMAXのサービス戦略を聞く(第1回)
2009年3月30日 0:00

対談:電波・周波数を語る(2):UWB/電子タグ(RFID)から802.11nまでの周波数
2006年11月13日 0:00