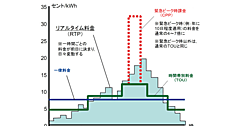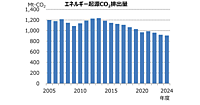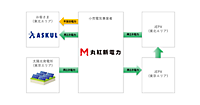より高度な機能へと進化・発展するデマンドレスポンス(DR)
─日本でも本格的な審議がスタート─より高度な機能へと進化・発展するデマンドレスポンス(DR)
以上見てきたように、DRの役割は、当初は、前述したTOU(季節別時間帯別料金制度)をはじめ、ピークの電力需要を下げるための仕組みであったが、アンシラリーサービス(表2脚注を参照)のような、さらに高度な系統安定化までをカバーする仕組みに発展しつつある。
例えば、前日通知のデマンドレスポンス(スロー・デマンドレスポンス)では、前日に電力会社からの電話を受けた大口需要家は、当日指定された時間に負荷を人手で削減する形がとられてきたが、スマートグリッドの発展と並行して、DR信号注3に対して、自動的に負荷を削減するハードウェアやソフトウェアが開発され、実用化が進んでいる。
このような、自動的にDRを行うADR(Automated Demand response)といわれる仕組みをうまく機能させるためには、まず、電力会社と需要家の間でやり取りするDR信号の規格を定める必要がある。さらに、電力会社や大口需要家が採用する異なるメーカーの機器・装置やソフトウェア間で、正しくDR信号の内容を理解し、それに対して規定に従って正しい応答を返す必要がある。
そのためにオープン標準を定め、異なるメーカーのDR製品間での相互運用性を保証するための機関として登場したのがOpen-ADRアライアンス注4で、現在OpenADR 2.0aプロファイル仕様書が公開されている。
DRに関連する規格としては、他に国際標準機関IECのCIM注5やZigBeeアライアンスのSEP 2.0注6もあるが、OpenADR 2.0注7では、それらの間の互換性も考慮しながら、標準策定が進められている。
日本の取り組み:スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会
なお、日本の経済産業省は、JSCA(スマートコミュニティアライアンス)内に、日本型スマートハウス・ビルのさらなる普及に向けて「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」を設置(2012年6月22日)したが、この検討会が取り組む課題のひとつとして「デマンドレスポンスシステム標準化の検討」が位置づけられ、現在活発な審議が行われている。
▼ 注3
DRを開始させるためのピーク電力価格や、削減目標のMW(メガワット)値、系統の安定度等を示す信号。
▼ 注4
2010年設立。本部は、カリフォルニア州パロアルト。
▼ 注5
CIM:Common Information Model、共通情報モデル。国際標準策定機関のIECが電力業務の発電から送電、変電、配電までのバリューチェイン内で交換される情報をモデル化したもので、その中にDRの情報モデルも含まれている。
▼ 注6
SEP 2.0:Smart Energy Profile 2.0。スマートハウスなどにおけるオープンなIPベースの電力制御用の標準アプリケーションプロファイル(機能)。
▼ 注7
OpenADR:Open Automated Demand Response。OpenADR 1.0は、米国ローレンス・バークレー研究所が運営するDRRC(デマンドレスポンス・リサーチセンター)が中心となって仕様を策定した、カリフォルニア州中心のローカル標準。これを受けて、UCAIug(注8参照)内のOpenSG(Open Smart Grid)技術委員会の下にあるSG Systemワーキンググループ内のタスクフォースとしてOpenADRタスクフォースが作られ、米国のDR標準作成のための要件整理が行われた。その要件を踏まえて、標準化団体のOASISがエネルギー関連システムの相互運用性標準である「Energy Interoperation Version 1.0」を公開。OpenADRアライアンスは、この仕様をベースに、さらに相互運用性を追求してOpenADR 2.0の仕様書づくりを行っている。
▼ 注8
UCAIug:UCA International Users Group、米国の電力会社の国際ユーザーグループ。UCAはUtility Communication Architectureの略。