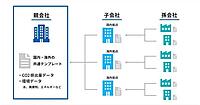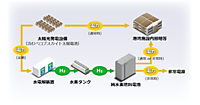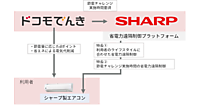対談:放送・通信融合を語る(2):放送と通信の技術的課題は何か?(2ページ目)
【3】非圧縮の「DVTS」標準規格を使う理由は?

—どのような映像の標準技術を使用しているのですか?
村井 現在は、DVTS(Digital Video Transport System。RFC 3189、RFC 3190)というIETFの標準規格を使用し、デジタル・ビデオの映像を非圧縮でそのままインターネットで流す(IP伝送する)ことが広く使われるようになりました。
この標準はシンプルですから、Windows用やApple用をはじめ、Linux用やBSD用など、プラットフォームの上で動くソースコードが全部開示されています。今アメリカの大学では、インターネットで映像アプリケーションを作ろうとするときに、一番シンプルなソフトウェアとして、たくさん使われています。最終的にこれが一番プリミティブな方法でした。つまり(時間方向の)圧縮などしないけれどもCPUが早くなってきたから、結構実用的になってきたのです。
DVTSは、カメラからの映像をインターネットに投げるだけで、なんと35Mbpsも帯域を使ってしまうわけです。先ほどの電話回線の64kbpsのストリームと比べると大違いですよね。数値的には、64kbpsから35Mbpsへと500倍以上も高速になっているのです。今この装置は、ケーブル・テレビで、裏で放送番組を流通させるために結構使われています。
このDVTSによる非圧縮の35Mbpsのビデオ配信に対して、きちんとH.264のような洗練された最新の圧縮技術が入ってきたら、かなり多様な映像のアプリケーションが作れるということになりますよね。以前、音声が見えてきたように、上限の見えにくかった映像も見えてきたという感じがしています。
—圧縮のご専門家である亀山先生は、DVTSと圧縮の関係についてはいかがですか?
亀山 私も、村井先生のDVTSに関する論文は読ませていただきましたが、そのとき、ある意味で「コロンブスの卵」だなと思いました。というのは、やっぱり圧縮屋さんは、基本的には限界まで情報を圧縮し、映像データができるだけ小さいほうが流れやすいと考えているところがあるからです。
たとえば、現在の地上デジタル放送やデジタル衛星放送の場合ですと、6Mbpsあるいは4Mbps程度で送るのが普通だろうとずっと思っていたわけです。それを村井先生は、時間方向には非圧縮のDVTSで35Mbpsで流すことを考えられた。ただ、村井先生がその論文を書かれたのが、確か5年くらい前ですよね。2000年の初頭くらいだったので、その時は「ウソでしょ!!」と思いました。正直言うと、私は35Mbpsでは情報を流せないと思っていたからです。
ところが、今(2006年)になって考えてみると、もう5年、6年経っているわけですね。最近は、数十メガくらいは普通に通るようなネットワークが、すでに我々の身の周りで使えるようになってきていますよね。
【4】次世代に渡したい、夢を実現できる環境!
村井 35Mbpsという高速なインターネットに接続されたコンピュータの上で、映像を自由にやり取りできるという環境のもと、プログラマーや、アイディアをもった次世代の人たちに、新しいことを思いついてもらいたい。その夢を持って何か挑戦してもらいたいというのが、僕の思いなのです。とりあえず何か新しいことを思いつく人に、そういう夢を実現できる大学の環境をきちんと渡したいのです。
亀山 学生は幸せですよね。
村井 そうそう、だからそう思って作ったのです。これが「インターネット2」(米国の次世代インターネットに関する産官学協同の研究開発プロジェクト)に参加するアメリカ中の大学に広まったということは、面白いし、日本ではもちろんのこと、中国でもものすごく使われているのですよ。
数年前に、日本でもJGN(Japan Gigabit Network、研究開発用ギガビット・ネットワーク、1999年~2004年)という高速なテストベッド・ネットワーク環境ができましたが、このネットワークの試験にも映像が大きな役割を果たしました。通常のアプリケーションではギガビット・クラスを必要としませんが、DVDであれば35Mbpsくらいは必要とするので、DV(デジタル・ビデオ)を何本か束ねることで比較的簡単にギガビットのありがたみがわかるようになります。
さらに医療画像情報なども情報量が多いので、テストベッド用に向いたアプリケーションでした。さらにハイビジョン(HD)の映像を圧縮しないでそのまま流す実験となると、1.5ギガビット(1.5Gbps)くらいは必要になってくるわけです。
—しかし、映像ストリームはもっと高解像度へ向かっていますね。
村井 それで、最近ではJGNから発展したJGN2(2004年~)の10ギガビット・ネットワークで実験しています。しかし、1.5Gbpsの非圧縮のHDよりももっと大きいスーパーHDを流すとなると、全然10ギガでは足りないのです。
このように、高速ネットワークが先に進んだときに、高速ネットワークのテスト用としても、実は映像のストリームというのは大事なのです。この映像ストリームの極限を、絶えず共有して研究する環境の中で、新しい映像を使ったサービスを考える学生がどんどん出てきてほしいのです。
そして、これが本当のビジネスになるときには、必ずもっと洗練された、圧縮技術や信頼性を高める技術などがでてくるわけです。
このような発想をもって、新しいサービスを作る次世代を担う学生に、早くから映像が自由自在に使える高速インターネットを経験させておかないといけません。5年早く経験しておけば、5年後には洗練された良いアイディアがやっぱり出てくる。そういうことなのです。