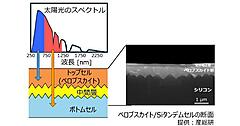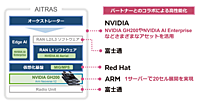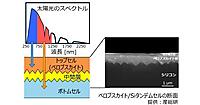放送・通信融合時代を迎えた今日、その現状と課題について、慶應義塾大学 環境情報学部 村井純教授と早稲田大学 大学院 国際情報通信研究科 亀山 渉教授に対談を行っていただきました。これまでの、
『<テーマ1>放送と通信はどこがちがうのか?』
『<テーマ2>放送と通信の技術的課題は何か?』
につづいて、今回は、
『<テーマ3>放送・通信融合時代の制度的・政策的な課題は何か?』
についてお話いただきました。(文中、敬称略)

慶應義塾大学 村井 純 教授 VS 早稲田大学 亀山 渉 教授
テーマ3
放送・通信融合時代の制度的・政策的な課題は何か?
【1】デジタル化は、ものごとの原点を問う!
—「通信・放送の在り方に関する懇談会」(通称:在り方懇)をどのように位置づけられていますか?
村井 私も参加していた竹中平蔵 総務大臣主催の「通信・放送の在り方に関する懇談会」(通称:在り方懇)の画期的なところは、放送のデジタル化を機会に、かなりタブー視されていた放送と通信関連のテーマに対して、政治的、制度的、技術的なことも含めて明示的に議論の対象になったということです。
例えば、放送のデジタル化を契機にして、『アナログとどこが違うのか?』、『インターネット(IP)に放送を乗せると何が悪いのか?』、『放送事業の免許との関係をどうすればいいのか?』というように、前に亀山先生がおっしゃったようなことが問われたりしました。
つまり、放送の誕生は技術ありきなのですが、サービスが登場するにつれて、いろいろな都合で、いろいろなルールができてしまった。そのルールを今、見直すことになったのです。一般に何かをデジタル化する場合には、原点に戻った議論をせざるを得ない場合が多々あるのです。
【2】制度面だけでなく技術的課題もある!
村井 放送のことに関して、私はよく「情報基盤としての対策などをサボっていただろう」と言われることがあります。アナログ通信だった電話は、きちんとまな板に乗せ、いろいろな議論をして、ADSLなども発達し開放も進み、また制度の改革も進みデジタル化されたのに、どうして放送はまだなのか?という意味だと思います。
しかし、放送などの無線のデジタル化に伴う環境整備が遅れた背景には、制度面だけでなく技術的な理由もあるのです。なぜかというと放送をデジタル化するときの技術的課題、つまり、
(1)電波をデジタル技術で上手に使う方法
(2)電波にデジタル情報を上手に乗せる方法
の2つについて、私たち技術者はまだ洗練された経験知を十分にもっていないのです。
たとえば、無線LANが普及したため、無線LAN(Wi-Fi)の電波からたくさんのコンテンツを、至るところから受け取ることができようになりました。また、携帯電話の基地局があちこちにできて、基地局の周りの携帯電話に十分なデジタル・データを同時に送受信できる環境が現実になったのもこの2~3年のことなのです。
こういう環境を実現するために、技術者は精一杯やってきましたが、まだ課題はあります。一方、制度的な面から見ると、技術の進歩との対比で制度をどこまで変えるのかという議論を本当にできたかというと、不十分な面があります。デジタル化をきっかけとして、5年前に電話でやったことを、今、放送でもすぐできるかと聞かれると、私は技術的にも制度的にもまだ用意できていない面がたくさんあると答えるべきだったと思います。
ですから、放送のデジタル化を契機に、放送と通信(インターネット)のあり方の議論が、今ようやくできるようになったというタイミングだと思います。