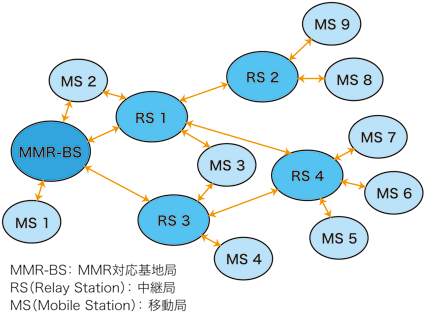【2】MMRの性能目標
802.16jは、802.16eの上位セットの規定である。MMR技術をネットワークに追加導入する際の性能目標は、提供するサービス・エリアにおけるユーザーのサービス・レベルを向上するなどの指標で表されるが、その具体的な要求値は展開モデルによって流動的である。
例えば、ビル内のカバレッジを拡大するモデルでは、展開によって拡大されるビル内のカバレッジと、要求する容量の総合値として表される。また、臨時利用モデルでは、一時的に必要とされるカバレッジと容量の総合値として示される。移動体への搭載モデルでは、車両内で必要とされる容量、リンク(回線)のSINR(Signal to Interference and Noise Ration、信号対干渉雑音比)の向上や、多重ルートによる信頼性の向上で示される。
MMRの性能目標の内容は、次の通りである。
(1)ユーザー・スループットの向上と容量、信頼性の拡張
802.16jの展開によって、ユーザー・スループットやシステム容量、信頼性の向上を図る手段として次の2つの方法がある。
▽セル・エッジへの中継器設置によるSINR向上
単一でSINRの低いリンクを、高次変調と高符号率化が可能なSINRの高いリンクに置き換え、周波数利用効率と容量の向上を実現するとともにリンクの信頼性を向上させる方法である。
より詳しく説明すると、セル・エッジは、文字通り基地局がカバーするエリアの最も外側であり、この場合は隣接の基地局とのオーバラップ(重複)・エリアが存在せずに、さらに外側に移動することで、基地局のサービス・エリア外になる場合を想定している。
このような場所では、最も近い基地局の電波がギリギリ届く状況で、伝搬路(パス)も複数を得ることが期待できない状態であり、SINRも低いことが推定される。SINRが低いとQPSK(4相位相変調)のような、伝送速度が低くなる変調方式を適用することが精一杯となる状態となる。
このような領域にMMRを適用することで、MSS(Mobile Subscriber Station、携帯端末)に対しては電界の強い電波を供給することができ、SINRの向上を図ることができる。SINRが高いと、16QAM(16値直交振幅位相変調)や64QAM(64値直交振幅位相変調)などの高次変調方式を適用することが可能になるとともに、ビット誤り特性も向上する。
このようなことから、誤り訂正の符号化を少なくすることが可能となり、さらに効率の高い通信が可能となる。その結果、スループットの向上やリンクの信頼性の向上を図ることを可能とするという考え方である。
▽小セル高密度配置による性能向上
中継器、MMR-BS(基地局)を小セルで高密度に展開するトポロジーによって、直接的に中継器のカバー・エリアの容量を増加し、ルーティング・ダイバーシチ(冗長性)を実現することでリンクの信頼性を向上させる。
ルーティング・ダイバーシチとは、簡単に言えば、小セル化することによって、端末に複数の基地局からの電波が受信できる状態をつくり、リンクの信頼性を向上させる技術である。
この場合、支配的となる通信相手である基地局が障害などで停止した場合にも、その近傍で運用する基地局からの電波を受信してサービスを継続することができることが想定される。
すなわち、基地局のカバレッジの冗長性を確保することになるが、これをネットワークの視点で見れば通信経路が多重化され、冗長化されていることと同等になるという考え方である。
(2)カバレッジの拡大
MMRの利用モデルごとの展開は次の通りである。
▽ビル影のカバレッジ拡大
高密度な都市環境において、高層ビルの谷間に生じるビル影に位置するユーザーへのカバレッジ提供のための展開。
▽基地局カバレッジ外でのエリア拡大
基地局からの電波が届かないエリアに位置するユーザーへのカバレッジ拡大を実現するための展開。
▽閉空間やトンネルでのカバレッジ拡大
高密度な都市環境やトンネル内において、端末(MS)を載せた移動車両(バスや列車)へのカバレッジの提供のための展開。
(3)想定トポロジー:3つのタイプ
図5は、前述の利用モデルを可能とするトポロジー構成のタイプとして示される。図5中の中継器は、固定(Fixed)、半固定(Nomadic)、移動(Mobile)の3つのいずれかのタイプに属する。
(4)中継器のオーナーシップ(設置当事者)
中継器のオーナーシップとしては、次のケースが想定される。
▽インフラ提供事業者がオーナーとなる場合
他の利用者のためにカバレッジを提供するケース(固定の利用者に対する中継器の展開)
▽ネットワーク利用者がオーナーとなる場合
自己の利用のためにカバレッジを提供して運用するケース(自分の部屋など)