空間場所情報システムの豊富な実演
「ユニバーサル社会」の実現に向けて
T-Engineフォーラム (ユビキタスIDセンター を含む)やYRPユビキタス・ネットワーキング研究所 の提唱するRFIDシステムの適用分野として特徴的なのが、モノではなく、「場所」にRFIDタグなどを取り付けて、その場所についての情報を提供しようという「空間場所情報システム」です。
この空間場所情報システムの具体例として挙げることができるのが、国土交通省などが推進する「自律移動支援システム 」です。自律移動支援システムでは、『すべての人が持てる力を発揮し、支え合って構築する「ユニバーサル社会」の実現に向けた取り組みの一環として、社会参画や就労などにあたって必要となる「移動経路」、「交通手段」、「目的地」などの情報について、「いつでも、どこでも、だれでも」がアクセスできる環境をつくっていくための検討を行うこと』を目的としており、2004年9月に神戸で実証実験をスタートしました。
その後、自律移動支援システムの実証実験に参加する地域が増え、「ゆきナビ青森プロジェクト」(青森県)、「東京都ユビキタス計画・銀座」(東京都)、「静岡おもいやりナビ実証実験」(静岡県)、「奈良自律移動支援プロジェクト」(奈良県)、「堺市自律移動支援プロジェクト」(大阪府堺市)、「世界遺産熊野古道ナビプロジェクト」(和歌山県)、「くまもと安心移動ナビ・プロジェクト」(熊本県)などの実証実験が行われています。
また、恩賜上野動物園(東京都台東区)や、デパートの伊勢丹(東京都新宿区)の屋上庭園(連載第1回を参照)では、動物や植物の情報を提供する手段として、これらの実証実験で使用されているのと同様なシステムを構築し、すでに実運用しています。

ユビキタス・コミュニケータの貸し出し
今回のTRONSHOWでは、「ユビキタス・ショーケース」というブースで、これら各地で行われている実証実験の雰囲気が伝わる展示が行われ、来場者は、「ユビキタス・コミュニケータ」と呼ばれる端末を借りて(写真2、写真6も参照)、展示コーナー内(写真3、4)を歩くことで実証実験の一部を体験することができました。
これらの実証実験で提供されるのは、観光情報、経路案内、踏切情報、店舗情報などで、RFIDタグ、QRコード、赤外線ビーコン(赤外線を使用して情報を発信する装置)などにより、利用者の状況(移動方法、使用言語など)や、利用者を取り巻く状況(場所、天候など)に応じた適切な情報が提供される仕組みになっています。
 写真3 静岡おもいやりナビ実証実験 |
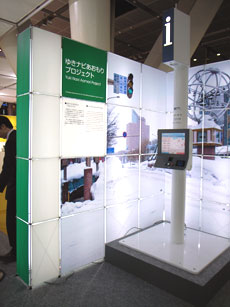 写真4 ゆきナビ青森プロジェクト |
光るタグ
医薬品の物流倉庫などで活躍
「光るタグ」は、YRPユビキタス・ネットワーキング研究所が開発したアクティブ型RFIDタグ「Dice」の発展形で、RFIDタグにLEDが取り付けられています(写真5)。これを無線基地局から呼び出すことで、特定の光るタグを光らせることができます。
この光るタグは、医薬品卸業の東邦薬品の物流センターにすでに導入されており、2006年11月から本格運用がスタートしています。

同社の物流センターでは、出荷にあたって、あらかじめ出荷の対象となる薬品を倉庫で集めておきます。集めた薬品は、一時的にスーパーなどで使用するようなカゴに入れておくのですが、このカゴに光るタグが取り付けてあります。
そして、伝票とカゴの対応を登録しておきます。このあと、コンベア上を折りたたみ式の通い箱(※業者間で再利用される物流用の箱のこと)が流れてくるのですが、通い箱は、それぞれ行き先(納品先)があらかじめ登録されています。
そこで、通い箱に貼り付けられた伝票のバーコードを読み取ると、薬品の入っているカゴに取り付けてある光るタグが光り、どのカゴから薬品を移せばよいかが、すぐにわかります。これにより、目的のカゴがすぐに見つかるようになったとともに、医薬品ではとくに問題となる通い箱への入れ違いがなくなったということです。
この光るタグは、429MHz帯の特定小電力無線を使用し、5台の無線基地局で最大800個の光るタグをリアルタイムで制御できます。電源には、リチウムイオン充電池を使用し、前述のような作業に使用するのであれば、フル充電で、1週間以上の連続使用が可能です。



















