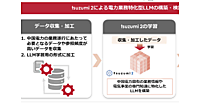アメリカのメディア企業PennWellは2018年1月23日、北米最大のエネルギー関連イベント「DistribuTECH 2018」を開催する。
アメリカのメディア企業PennWellは2018年1月23日、北米最大のエネルギー関連イベント「DistribuTECH 2018」を開催する。会期は25日までで、会場はテキサス州サンアントニオ市の中心部にあるHenry B. Gonzalez Convention Center。今回で28回目の開催となり、世界中からエネルギー関連事業者が集まるイベントだ。
図 「DistribuTECH 2018」の会場となるHenry B. Gonzalez Convention Center

出所 Henry B. Gonzalez Convention Center
DistribuTECH 2018の講演リストを見ると、IoT(Internet of Things)やGoT(Grid of Things)、大規模蓄電池などをテーマとしたものが多い。中でも、IoTやGoTで実現するスマートシティやマイクログリッドに関する講演に注目が集まりそうだ。
その中で、「Utility 3.0」を大きなテーマとして出展するのが日立製作所のグループだ。Utility 3.0とは、「Decarbonization(脱炭素化)」「Decentralization(分散化)」「Digitalization(デジタル化)」などの社会の流れによって電力事業者などの公益事業者が社会基盤を支える形に進化した状態を指す言葉だ。再生可能エネルギーを柔軟に活用できるスマートグリッド、スマートシティの実現とも言い換えることができそうだ。
電力事業者を例に取れば、「Utility 1.0」は、政府の規制などの保護を受けて経済成長を支えてきた時期を指し、「Utility 2.0」は、自由化により発電や小売りの競争を繰り広げる時期だ。現在の日本の電力事業者はこの段階にある。
「パリ協定」で各国が合意したCO2排出量削減目標を達成しながら、社会が求めるエネルギーを十分に供給するにはUtility 3.0の実現は必要不可欠と言える。つまり、化石燃料を大量消費して大電力を生み出す大規模火力発電所に頼る体制から、定置型蓄電池や電気自動車、太陽光発電、風力発電などの分散型のエネルギー源を柔軟に活用する社会へと変革していかなければならない。そのときに必要になるのがIoTやGoTなどの通信技術とコンピューター技術というわけだ。
日立グループは「Towards Realizing Utility 3.0」(Utility 3.0の実現に向けて)をテーマに、さまざまな技術や製品を出展する。例えば、需要家に近い位置で稼働する分散型のエネルギー設備「Grid Edge」や、配電業者向けシステム、そして日立製作所のIoT基盤である「Lumada」を活用したUtility 3.0の実現に向けた構想などを展示する。
図 「DistribuTECH 2018」における日立グループのブースのイメージ

出所 日立製作所
日立グループの展示には日立製作所のほか、同社のアメリカ法人であるHitachi America、IoT関連技術やデータ解析技術を手掛けるHitachi Vantara、さらに日立パワーソリューションズ、THEパワーグリッドソリューションが参加する
関連記事

― 米国最大級の電力業界関連のイベント「DistribuTECH 2016」速報 ― 22社によるOpenFMB(EnergyIoT)のデモが開催!
2016年2月12日 0:00

加速するDER(分散型エネルギー源)のグリッドへの取り込みの流れ
2018年4月1日 0:00

東京電力パワーグリッド株式会社 取締役副社長 岡本浩氏に聞く!日本の電力システム改革と今後の展望
2019年1月8日 0:00

日立など、米国でコンパクトな1MWコンテナ型蓄電システムによる実証プロジェクトを開始
2015年2月26日 0:00
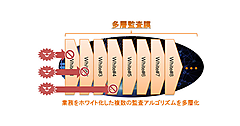
NEDOと日立製作所、攻撃の兆候を検知するアルゴリズムを新たに開発ー重要社会基盤に向けて
2017年10月2日 0:00

CPS/IoT時代を拓く次世代テクノロジーが勢ぞろいした‘CEATEC JAPAN 2016’
2016年11月10日 0:00