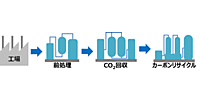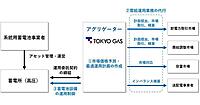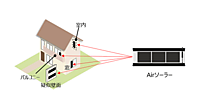開発の“現在位置”を見る!
― 実証実験見学会における一問一答 ―
「ペロブスカイト太陽電池 環境省実証事業開始式」では実証実験会場の見学会も行われ、実証実験場に設置されたPCSパネル群をバックに、マクニカの阿部氏と各メディア記者との間で質疑応答(Q&A)が行われた。そのやり取りの中から開発の“現在位置”を見てみよう。
Q(メディア記者、以下同): 実験施設(写真2)にはまだスペースがあるが、最終的に何枚のパネルを貼るのか。
A(阿部氏、以下同):最終的には80枚程度の予定です。現在、ペロブスカイトの構造体やフィルムへの塗布方法、封止材などが異なる種類のPSCパネルを装着して実験しています。よく見ると、ペロブスカイト(PSCパネル)の色が微妙に違うのでわかると思います。現在、他の種類のPSCパネルに関しても製造を進めており、でき次第、順次貼りつけて実証していきます。
Q:最終的に今回の実証実験で総発電容量1kW程度の発電を目指すと言っていたが、見込みはどうか。
A:まだまだ開発途中で、PSCパネルの種類によってはパフォーマンスにばらつきがあるのですが、今後改善を重ねて性能を安定させ、その程度の発電容量を達成したいと考えています。
Q:PSCパネルの発電効率はどのくらいか。
A:今回の実証実験に使用しているPSCパネルは、ロール・ツー・ロール方式で製造したものです。まだ、PSCパネルの種類によってばらつきがあり、またPSCパネルのサイズとの関係もあって、安定した一定レベルの発電効率を出せるようになるのはこれからです。今後トライを重ね、最終的には15%程度(前出の図1参照)の発電効率を出したいと考えています。ちなみに研究室でのチャンピオンデータでは、20%程度を記録しているものもあります。
Q:フィルム型PSCパネルの耐用年数はどのくらいか。
A:今回の実証段階での目標値としては10年を設定しています。今後開発を進め、最終的には15年程度を実現したいと考えています。
Q:PSCパネルのサイズは縦30cm×横100cmだが、その理由は何か。
A:サイズが大きくなれば、ペロブスカイトの塗工が難しくなります。生産性と発電効率の関係から、現状ではこのサイズに落ち着いています。ただ、今後の技術開発の動向では変わる可能性もあります。
Q:PSCパネルについて先ほど2通りの装着・脱着方法を実証しているとのことでしたが。
A:ご紹介したように丸パイプ方式とフラットバー方式の2通りで装着しています。構造によってPSCパネルを張る力が変わるため、それが発電にどのように影響するかを見ています。
またご覧の通り、この実証実験場は吹きさらしの環境なので、夕方になるとかなり強い風が吹きます。台風のときなどは、自動販売機が転倒するほどです。そのような環境にも耐えられるかどうかも検証します。図3に示すように、ペロブスカイトなどの有機薄膜系の太陽電池パネルは使用例が少ないため、装着方法も確立されていないのです。今回、その最適解を見つけたいと思っています。
Q:外部の電力系統との接続も予定していると発表があったが、すでに接続されているのか。
A:まだです。今回の実証実験はまだ外部の電力系統と接続していない独立電源方式となっています。現在、外部との接続のためのシステムを構築中で、次年度(2025年度)に実証を行う予定です。
Q:このPSCパネル実証実験で発電した電力は、どこで使っているのか。
A:写真2左側の実験場上部に「ペロブスカイト太陽電池 実証中」という看板照明を設置していますが、それをペロブスカイトの電気で点灯させています。また、その実験場の裏側に設置された蓄電池の上部(写真2右側)に実証実験のデジタルサイネージ「ペロブスカイト太陽電池 実証実験実施中」を設けていますが、その電源としても使用しています。
Q:蓄電池が3台設置されているがその容量はどのくらいか。
A:実証実験の動作状況の検証用に、とりあえずリチウムイオン蓄電池を3台(計3.6kW。写真2右側)設置しています。今後、発電容量が増えるので拡充する予定です。
(以上、実証現場でのやり取りをもとに編集部で構成)