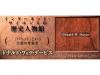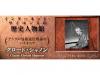戦後の研究体制の整備を提言
ブッシュがルーズベルト大統領に提案した事柄は、1947年2月に法案化されて上下院を通過したが、戦後の緊縮財政を重視したトルーマン政権は拒否権を行使した。しかし、ブッシュは同年9月に成立した国家安全保障法の研究開発評議会の議長に選任され、戦後の研究体制の整備を訴え続けた。
1948年8月にソ連が最初の核実験を行うと、ブッシュは国防総省から科学者のパネルの議長になることを要請され、科学者による諮問委員会を編成した。ブッシュは水爆の開発には反対の立場をとったが、ソ連との競争で優位に立つためには、研究開発に対する政府支援と軍の研究計画の統合が不可欠だと訴えた。この主張は1950年の米国科学基金(NSF:National Science Foundation)の設立を促し、ブッシュは初代ディレクタを3年間勤め、その後も2年間諮問委員として運営に関わった。
ブッシュの提言はARPAとNASAの創設へ
ソ連は1957年10月4日、人工衛星スプートニクを打ち上げて米国に衝撃を与えた。ブッシュは同年11月にリンドン・ジョンソン上院議員が召集した軍事サービス小委員会で、「米国は、数多くの有益かつ困難な仕事が必要な熾烈な競争の最中にあることを認識すべきだ」と語った。
アイゼンハワー大統領はこの提言に応えて、国防総省のARPA(高等研究計画局)と宇宙開発機構のNASA(米航空宇宙局)を創設することを決めた。ARPAは1958年1月7日に議会の予算承認を得て、2月7日に発足した。
民間の科学研究を支援するNSFと、軍の研究活動を統合するARPAが設立されたことにより、ブッシュが提唱し続けた軍産学の協力体制の礎が築かれ、米国におけるコンピュータ・サイエンスとインターネットの発展が支えられることになる。
ブッシュのビジョンに影響を受けた後進たち
1962年10月1日にARPAに着任して情報処理技術の責任者になったJ. C. R. リックライダーは、1965年に「未来の図書館」を著し、ブッシュの夢をデジタル・ネットワークの世界へと拡張した。ブッシュのMemexに感銘を受けたダグラス・エンゲルバートは、1968年にマウスでハイパーリンクを操作できる文書処理や、ビデオ会議が可能なオンラインシステムを実演し、来るべき情報化の時代を示した。
さらに、テッド・ネルソンは、1960年にブッシュのアイデアをヒントにして、「ハイパーテキスト」という言葉を生み出し、地球規模のネットワークで多様な情報をリンクで結ぶ「ザナドゥ(Xanadu)」でWebさながらの未来像を描いた。
ブッシュは1964年、ジョンソン大統領から科学大賞(National Medal of Science)を授与されたが、ベトナム反戦活動の矛先はブッシュにも向けられ、しばしば批判の矢面に立つことになった。ブッシュは戦後の対ソ連封じ込め政策を受け入れ、米国の軍産学複合体を象徴する人物でもあったからだ。
1969年7月に妻に先立たれたブッシュは、反戦活動の喧噪渦巻く1971年、MITの名誉学長を辞した。ブッシュの体力はその後急速に衰え、1974年6月30日、自宅で脳出血と気管支炎により倒れ、84年の生涯を閉じた。
参考文献
・G. Pascal Zachary「ENDLESS FRONTIER: Vannebar Bush, Engineer of the American Century」The MIT Press 1999
・David A. Mindel「Between Human and Machine: Feedback, Control, and Computing before Cybernetics」The Johns Hopkins University Press, 2002
・W. Aspray, A. G. Bromley, M. Campbell-Kelly, P. E. Ceruzzi, M. R. Williams「Computing Before Computer」 Iowa State University Press, Ames, Iowa 1990
・Robert Buderi 「The Invention That Changed the World: How A Small Group of Rader Pioneers Won the Second World War and Launched a Technological Revolution」 Touchstone, 1997
・岩山知三郎「汎用計算機と仮想空間の先駆者 バネバー・ブッシュ」、『月刊オープン・エンタープライズ・マガジン』、2005年9月号、(株)ソキウス・ジャパン