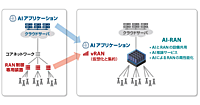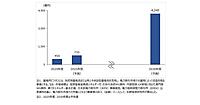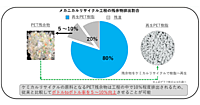今後の展開:分散型エネルギープラットフォームとして
〔1〕再エネの大量普及時代の自立電源として活用
ここまで、
- 大容量の蓄電池をベースにした米国カリフォルニア州サンディエゴにおける、系統線による「NEDOのマイクログリッドの実証事業」、
- 自営線を活用し実運用している「CHIBAむつざわエナジーのマイクログリッド」、
- 日本政府が推進する系統線を活用した地域マイクログリッド構築支援事業における「関電工のいすみ市地域マイクログリッド」
を見てきた。
これらのマイクログリッドはいずれも、従来の広域的で大規模・集中型の電力系統システムに比べて、地域に閉じた比較的小規模な「エネルギー供給システム」である。そのため、大規模な電力系統システムが災害によって停電を引き起こした場合などでは、系統から切り離して自立電源として活用できるという利点は大きい。
〔2〕分散型エネルギープラットフォームとして期待
マイクログリッドは歴史的にも多くの研究がなされ、実証も行われてきたが、そのシステム規模や形態などについて、厳密な定義がなされているわけではない。
マイクログリッドは、1999年に米国エネルギー省(DOE)傘下のローレンスバークレー国立研究所(LBNL:Lawrence Berkeley National Laboratory)が中心となって、大学や電力会社、メーカー、公的研究機関などが参加するCERTS(Consortium for Electric Reliability Technology Solutions、電力供給信頼性対策連合)によって提唱された。このCERTSでは、マイクログリッドを次のように定義している注18。
- 複数の小さな分散型電源と電力貯蔵装置、電力負荷がネットワークを形成する1つの集合体
- 集合体は、系統からの独立運用も可能であるが、系統や他の「マイクログリッド」と適切に連系することも可能
- 需要家のニーズに基づき、設計・設置・制御される
ここでいう「分散電源とは」太陽光発電や非常用電源など、「電力貯蔵装置とは」大容量な定置型蓄電システム(蓄電池)など、「電力負荷とは」需要家側(家庭等)の照明器具やエアコンなどと、それぞれ置き換えると理解しやすい。
今後、CO2排出量ゼロの再エネを主力電源として普及させるうえで、マイクログリッドが「平常時でも非常時(停電時)でも」経済的なコストで構築でき、品質の良い電力を効率よく安定して供給できる「分散型エネルギープラットフォーム」として普及していくことに期待したい。
▼ 注18
出所 経済産業省・資源エネルギー庁「地域マイクログリッド構築のてびき」(2021年4月16日)の12ページ