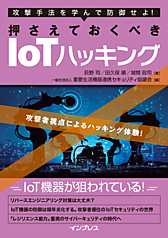はで始まるスマートグリッド用語
2014年10月29日 (水曜) 20:39
クリックすると、その文字から始まるスマートグリッドの用語をすべて表示します。
バイオマス
- [Biomass]
- 読み方-
- 内容再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの
生物資源の量を指す概念で、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものを指す。具体的には、廃棄される紙や家畜排泄物、食品廃棄物、籾殻、稲わら、さとうきびやトウモロコシなど多岐にわたる。これらから得られるエネルギーをバイオマスエネルギーと呼ぶ。
バイオマス発電
- [Biomass Power Generation]
- 読み方バイオマスはつでん
- 内容植物などのバイオマスを使って発電する方式
植物などのバイオマス(生物体)から固体燃料や液体燃料、気体燃料を製造し、今までは利用されてこなかったエネルギー源を使って発電する方式。例えば、バイオマスは、木くずや家畜の糞尿など、本来であれば廃棄されるような物質をエネルギー資源として利用できるため、化石燃料に代わる新エネルギー源として注目されている。
配電
- [Power Distribution]
- 読み方はいでん
- 内容電気の輸送方法である「送電、変電、配電」の内のひとつ
消費者に近い、電力会社の最終的な配電用の変電所から受電した電力(電気)を、一般家庭やビル・工場などの需要家に電力を供給するシステム(配電網システム)のこと。配電系統の主要な電圧は、例えば、日本では6.6kV の高圧配電線が工場やビルに配電される。さらに、電信柱などに設置された柱上変圧器で6.6kV をさらに降圧し、低圧配電線として100/200Vの引き込み線によって、一般家庭などに配電される。
バイナリー発電
- [Binary Cycle Power Plant]
- 読み方バイナリーはつでん
- 内容2つの熱サイクルを利用して発電する方式
加熱源によって沸点の低い媒体を加熱・蒸発させてその蒸気でタービンを回す方式。「加熱源系統」(例:熱水)と「媒体系統」〔例:代替フロン(HFC:Hydro Fluoro Carbon)〕の2 つの熱サイクルを利用して発電することから、バイナリーサイクル(Binary Cycle)発電と呼ばれており、地熱発電などで利用されている。また、工場等から出される、低温のため使われていない廃熱水(150°〜160°程度)の「熱水」で沸騰するような「媒体」(例:ペンタン。沸点36度)を利用して、タービンを回して発電する仕組みもある。この場合も、水(熱水)とペンタンの2つ(バイナリー)の流体(系統)を利用することから「バイナリー発電」と言われる。
発送電分離問題
- [Problem of Unbundling Generation and Transmission Services]
- 読み方はつそうでんぶんりもんだい
- 内容「発電事業と送電事業」を分離し、発電事業に参入しやすくすること
発送電分離問題とは、現在の10電力会社の発送配一貫体制(発送配:発電・送電・配電)によって運営され、地域独占形態となっている電力会社の「発電事業と送電事業(配電も含む)」を分離し、新規参入企業が、発電事業に参入しやすくし、完全自由化すること(現在、一部自由化)。このため、電力を需要家(家庭等)に送るインフラ部分である送電部門・配電部門を担う新「送配電会社」は、どの電力事業者の電力も公平に送るよう中立性が求められる。政府では、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故の教訓(計画停電の実施等)から、電力を安定的に効率よく、安価に提供できる発送電分離を実現する検討(電力制度の改革)が行われている。同時に、一般家庭への電力小売りの完全自由化も検討されている(現在は一部大口需要家のみ自由化)。これによって消費者は、電力の小売り部門から、例えば自分の好みの電力会社を選択したり、太陽光発電あるいは風力発電等によって発電されたクリーンな電力を選択して、使用できる可能性も出てくる。この課題は、経済産業大臣の諮問機関である「総合資源エネルギー調査会」に新設された「電力システム改革専門委員会」(2012年1月設置)で審議されている。
発送電分離と4タイプ
- [4 Types of Unbundling Generation and Transmission Services]
- 読み方はつそうでんぶんりと4タイプ
- 内容会計分離/所有分離/法的分離/機能分離
電力会社の発電部門と送電部門(配電も含む)を分離することを「発送電分離」という。この場合、電力市場に参入する新規の発電会社が、不利にならないように、送配電部門を分離独立させる(例:送配電専門会社の設立等)必要がある。その場合、設立された送配電専門会社は、発電会社を問わず電力を公平に扱い、需要家に送る中立性が求められる。現在、発電部門と送配電部門を分離する場合、次の4 つのタイプが検討されている。
(1)会計分離タイプ:現在行われている電力会社の発電部門と送電部門の各会計の分離を徹底させるタイプ。
(2)所有分離タイプ:電力会社が、送配電部門を完全に切り離して別会社化するタイプ。
(3)法的分離タイプ:電力会社が、例えば、持ち株会社のもとに発電部門と送電部門を分社化するタイプ。
(4)機能分離タイプ:送配電網の運用を第三者の中立組織(専門会社等)に任せるタイプ
発電
- [Power Generation]
- 読み方はつでん
- 内容電気を発生させること
通常、大型の発電所では、磁石をコイルの中で回転させる(モーターを回す)と電圧が生じる「電磁誘導現象」の原理を用いて、発電するものがほとんどである。この回転させる力を何のエネルギー(水力・ウラン・石油等)から得るかによって、(1)水力発電〔水でモーター(発電機)を回す(注)〕(2)原子力発電〔ウランを燃やして得た蒸気でモーター(発電機)を回す〕(3)火力発電(石油・ガスを燃やして得た蒸気でモーター(発電機)を回す〕などの発電方式がある。火力発電や原子力発電の発電電圧は、1万V〜2.5万V 程度である。最近では、太陽光発電や、風力発電など、再生可能エネルギーを利用した小型の分散型の発電方式が普及し始めている。
(注)通常、タービン(羽根車)に、水(水力発電の場合)や蒸気(火力・原子力)をあて、タービンと直結した発電機(モーター)を回して発電する。
パワーコンディショナー
- [Power Conditioner]
- 読み方-
- 内容-
PCS(Power Conditioning System)[→]
ハワイマウイ島の離島型スマートグリッド実証事業
- -
- 読み方ハワイマウイとうのりとうがたスマートグリッドじっしょうじっけん
- 内容NEDOが参加し実施している実証事業
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が参加し、実施している実証事業。経済産業省傘下のNEDO は、ハワイ州マウイ島で離島型クリーンエネルギー社会モデル(離島型スマートグリッド)を構築することを目的に、ハワイ州、ハワイ電力、ハワイ大学、米国国立研究所などと共同で離島型スマートグリッド実証事業実施する。この共同実証事業の事業期間は2014年度までの4年間、予算は30億円の予定。日本の事業委託先は、日立製作所、みずほコーポレート銀行、サイバーディフェンス研究所の3社を決定(2011年11月2日発表)。具体的には、再生可能エネルギーの導入が進んでいるハワイ州マウイ島で、再生可能エネルギーの出力変動による周波数への影響、および配電系統の電圧問題などの問題を解決するため、マウイ島のキヘイ地区にスマートグリッド環境を構築する。さらに、マウイ島を走る電気自動車の充電のタイミングを調整するマネジメントシステムを構築し、実証する。
バンドル
- [Bundle]
- 読み方-
- 内容OSGiのモジュール単位
ホームゲートウェイなどのシステムを構築するための技術である「OSGi」[→]のモジュール単位。アプリケーション開発者はバンドル〔アプリケーションに相当する実行単位のことをOSGiでは「バンドル」(Bundle)と呼ぶ〕を作成してOSGiのプラットフォームに配備する。そして、複数のバンドルが連携し合ってアプリケーションを形成する。
基本的にバンドルには、(1)OSGiアライアンスであらかじめ仕様が決められた標準サービスを提供するバンドル(ログサービスバンドル、HTTP サービスバンドル等)(2)利用者が独自に開発するアプリケーションバンドル(プリンタ制御バンドル、カーナビ制御バンドル等)の2 種類がある。