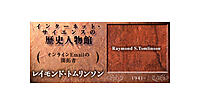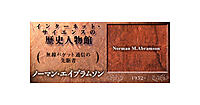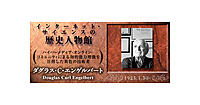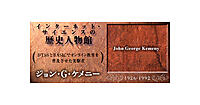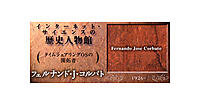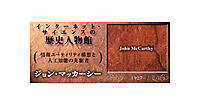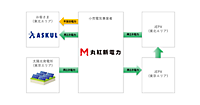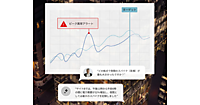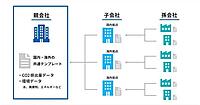ARPAへの入局ミサイル防衛管制システムの開発へ
ARPAへの入局
ミサイル防衛管制システムの開発へ
リックライダーは1962年の初めに、国防省高等研究計画局(ARPA)の局長ジャック・ルイナに請われて、ワシントンD. C.を訪れた。
ARPAは、旧ソ連がスプートニクを打ち上げ、科学技術の重要性を再認識したアイゼンハワー大統領が創設を提案し、議会の承認を経て、1958年2月7日に発足した。空軍次官だったルイナは、ケネディが1961年1月に大統領に就任して、ARPAの局長に任命された。ケネディは1961年3月に、大陸横断弾道ミサイル防衛のための高度な指令管制システムの必要性を議会に訴え、予算の承認を求めた。
ARPA局長のジャック・ルイナは、1961年6月に指令管制システムの研究プロジェクトを開始することになり、SAGEのコンピュータ「AN/FSQ-7」のスペアマシン「AN/FSQ-32」を4台所有していたSDC(System Development Corporation、世界最初のソフトウェア開発会社になる)に、1台のマシンを利用して新プロジェクトのために年間600万ドルの予算を配分した。
ケネディの指令管制システムは、気象予報、諜報活動、兵站(へいたん)、通信、戦闘シミュレーション、訓練などに情報処理技術を適用し、不測の事態に対して局所的な防衛能力を最大化することを要請していた。ルイナは、専門家による諮問委員会を形成し、11月にARPAが研究を主導してコンピュータと通信の技術を底上げすべきだとする報告書を受け取った。報告書は、行動科学の研究の必要性も指摘していた。
ルイナは、コンピュータと行動科学を組み合わせたプロジェクトを監督できる人材に思考を巡らせて、以前会ったことがあるリックライダーを思い出した。リックライダーは空軍の技術諮問委員を6年つとめ、SAGEプロジェクトに最初から参加した心理学者だった。
しかも、彼は「人とコンピュータの共生」で、研究すべきテーマを示していた。リックライダーは年間1,000万ドルの予算を提示され、1962年10月1日からARPAで働くことに合意した。
研究者コミュニティの創設を構想
リックライダーがARPAに入所した直後の10月14日、キューバに旧ソ連の中距離弾道ミサイルが配備されたことが判明し、核戦争が現実になるという恐怖感が全米に広がった。リックライダーは、当時最も強力なコンピュータを保有していたSDCとMITで、タイムシェアリング・システムを実現し、その周りに他の大学の優秀な研究者のコミュニティを形成して、研究課題に総合的に取り組める体制を築くことを構想した。
リックライダーは、エド・フレドキンをコンサルタントとして雇い、1962年11月、SDCでタイムシェアリングに関する会議を開いた。この会議では、Q-32をバッチ処理に使用していたSDCの責任者とともに、マービン・ミンスキー、ジョン・マッカーシー、フェルナンド・コルバットゥ、ベン・ガーリー、アラン・パーリスらが顔を揃えた。
リックライダーはこの会議で、SDCにタイムシェアリングの意義を認識させ、すでに年間600万ドルを投じている指令管制システムの開発の土台に、タイムシェアリングOSを据えた。SDCではその後すぐに、ジュールス・シュワーツをリーダーとする約10人のグループが、タイムシェアリングOSの開発に着手した。
リックライダーはSDCを訪問した後、スタンフォード大学のジョン・マッカーシーと、カリフォルニア大学バークレー校のエド・ファイゲンバウムに会い、タイムシェアリング・システムと人工知能のプロジェクトについて話し合った。
ダグラス・エンゲルバートからの提案
ロバート・ファノとの出会い
リックライダーが国防省に帰ると、カリフォルニア州メンローパークのシンクタンク、SRI(Stanford Research Institute、スタンフォード研究所)のダグラス・エンゲルバートからの提案書が届いていた。エンゲルバートは、リックライダーの「人とコンピュータの共生」に共鳴し、人類の知的活動能力を高めるコンピュータの利用法を考察していた。
リックライダーは、1962年にサンフランシスコで開催された春期合同コンピュータ会議で、エンゲルバートと少し話しをしたことがあった。エンゲルバートはリックライダーがARPAに移ったことを知って、自発的に研究プロジェクトの提案書を書いた。
次いで、リックライダーは、MITRE(1958年にMITリンカーン研究所の役割を継承するために設立された非営利団体)がバージニア州ホットスプリングで開催した指令管制の会議に参加し、最終日の11月21日にMITのロバート・ファノとワシントンに向かう列車の中で、指令管制とタイムシェアリング・システムについて語り合った。
ファノは、1939年にイタリアから亡命してきた電気工学の研究者で、戦後はクロード・シャノンの通信の数学理論を教える役割を担い、MITの長期研究委員会のメンバーも務めていた。ファノはコンピュータの専門家ではなかったが、デジタル計算の原理は理解していた。
ファノは、MITがタイムシェアリングによる情報ユーティリティのパイロット・システムを、ARPAの支援で実現できる可能性を考えた。MITでは1961年の創立100周年記念講演で、人工知能の創始者の1人ジョン・マッカーシーが、コンピュータ・ユーティリティという言葉を使い、電話のように誰もが利用した分だけ料金を支払うコンピューティングの未来像を語っていた。ファノは2ページの提案書を書き、11月26日にMIT総長ジュリアス・ストラットンをはじめとする幹部に配布した。ファノは総長の同意を得て、キャンパスの近くにある9階建てのビル、ケンブリッジ・テクノロジー・スクウェアの8階と9階でプロジェクトを開始することになった。
関連記事
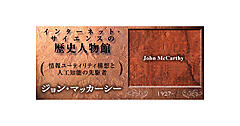
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(12)ジョン・マッカーシー
2008年1月29日 0:00
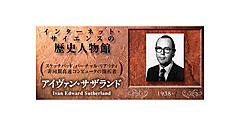
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(3)アイヴァン・サザランド
2006年11月28日 0:00
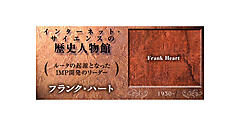
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(10)フランク・ハート
2007年11月20日 0:00
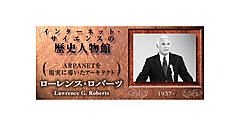
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(8)ローレンス・ロバーツ
2007年10月3日 0:00
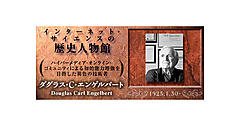
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(15)ダグラス・カール・エンゲルバート
2008年4月15日 0:00
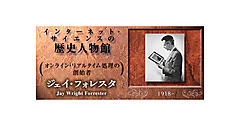
連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(5)ジェイ・フォレスタ
2007年2月2日 0:00