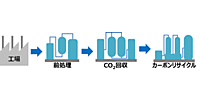次世代アプリケーション:PoEを活用したネットワーク
オーディオ設備音響への応用
〔1〕従来の設備音響
ヤマハでは、PoEを活用した次世代アプリケーションとして、ネットワークオーディオ設備音響への応用を検討している。設備音響とは、オフィスビル構内、レストラン、宴会場・会議場、商業施設などの施設内に組み込まれた音響機器の総称である。
従来の設備音響では、図11に示すように、オーディオとデータは完全に分離されており、オーディオの配線は端子盤を使って行われている。
このため、音場(音を伝える領域)の変更は端子盤などの物理配線やオーディオプロセッサ、オーディオアンプ(増幅器)の設定変更などによって実現していた。その結果、設備工事費が高くなるとともに配線が複雑となるため、故障時の修復などにも時間がかかるという問題があり、シンプルな配線が求められていた。
図11 従来の設備音響の構成例

〔2〕ネットワークオーディオの実現例:ネットワークオーディオ
そこでヤマハでは、新しいビジネスとしてネットワークオーディオ対応機器の開発に取り組んでいる。
ネットワークオーディオとは、図12に示すように、スイッチングHUBに接続されたデータ通信用のイーサネットケーブルを使用して、オーディオを伝送する技術である。すなわち、既存のIPネットワーク上で、データ通信とオーディオ配信が共存できるシステムでもある。これによって、複数のスピーカーに対する音を1本のケーブルで伝送することが可能となり、また、音声の接続先のスピーカーをソフトウェアによって変更できることも大きな特徴である。
図12 ネットワークオーディオの実施例

このネットワークオーディオによって、
- 端子盤間のケーブル集約注1
- データ通信ネットワークとの配線の共用
- 配線システムの集中管理
- 端末の状態の監視
- 音場変更の自由度の向上、施設内の自由なオーディオ配信
などが可能になり、従来の配線システムを大幅に簡略化できる。
〔3〕ネットワークオーディオへのPoEの適用
(1)PoE給電オーディオノードによって可能になること
最後に、前述した図12の天井スピーカーに、PoE+ネットワークオーディオモジュールを搭載した「オーディオノード」を使用した例が図13である。
図13 PoE給電オーディオノードを搭載した天井スピーカーによるシステム案

PoE給電オーディオノードによって可能になることは、
- ①イーサネットケーブル1本の配線で済むこと
- ②オーディオノードのインテリジェント化によって、ネットワークオーディオや自己診断・通知などが可能となること
- ③PoEスイッチ制御によるリモート電源制御が可能になること
- ④PoE給電ネットワーク機器とのインフラを共通化できること
などである。
(2)PoE給電オーディオノード普及への課題
また、PoE給電オーディオノード普及への課題として、以下が挙げられる。
- ①コストの問題:各ノードにPoE+ネットワークオーディオのモジュールが必要となるため、安価な天井スピーカーなどではコストアップが大きくなること
- ②各スピーカーへの配線がPoE導入前と比較して減らないため(アナログケーブルからイーサネットケーブルへの変更のみ)、従来のような使用方法では大きなメリットがないこと
このため、ネットワークオーディオへのPoEの適用は、PoE+ネットワークオーディオのモジュールのコストダウン、およびPoE構成を活かした魅力的なアプリケーションの提示が普及への鍵となると見られている。
◎取材協力

曽根 卓朗(そね たくろう)氏
ヤマハ株式会社 研究開発統括部 第2研究開発部 部長
北海道大学 工学部応用物理学科卒業。
1982年 日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)入社。組込み機器のシステム設計及びソフトウェア開発を中心とした製品開発と研究開発に従事。
2013年8月より研究開発統括部 第2研究開発部 部長。

冨永 聡(とみなが さとし)氏
ヤマハ株式会社 研究開発統括部 第2研究開発部 技師補
東京工業大学大学院 総合理工学研究科物理情報工学専攻修士課程修了。
1991年 ヤマハ株式会社入社。音源LSI開発、ルータVoIP開発などを経て、2012年からネットワークオーディオ導入を担当。

木村 俊洋(きむら としひろ)氏
ヤマハ株式会社 SN開発統括部 第2開発部 技師補
大阪大学大学院 基礎工学研究科情報工学専攻修士課程修了。
1997年 ヤマハ株式会社入社。ルータ等のネットワーク機器のソフトウェア開発を経て、ネットワーク分野の要素技術開発に従事。
▼ 注1
図11の端子盤の場合、上の端子盤からゾーンAの端子盤までの間にzのアナログ配線のケーブルåが通る。これをUTPケーブルに集約できる、ということ。