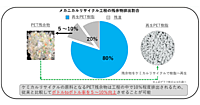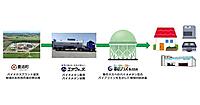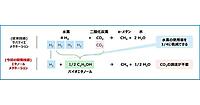デジタル化/オールIP化による放送・通信融合時代を迎えた今日、その現状と課題について、慶應義塾大学 環境情報学部 村井純教授と早稲田大学 大学院 国際情報通信研究科 亀山 渉教授に対談を行っていただきました。村井教授は、広く日本の「インターネットの父」として知られ、世界最大のインターネット・プロジェクト「WIDEプロジェクト」の代表として国際的に活躍中です。亀山教授は、MPEGの標準化をはじめTV-Anytimeフォーラムの副議長として国際的に活躍され、現在はデジタル放送の研究、モバイルマルチメディア通信研究の分野で活躍中です。(文中、敬称略)

慶應義塾大学 村井 純 教授 VS 早稲田大学 亀山 渉 教授
テーマ1
放送と通信はどこがちがうのか?
【1】デジタル化で、放送と通信の共通基盤ができた!
—放送と通信の融合について、技術的にも制度的にも大きな話題を呼んでいますが、現状をどのように整理してとらえておけばよいのでしょうか?
村井 放送と通信の関係が発展する背景には、明らかにひとつの大きな前提があると思います。それはデジタル化の流れです。インターネットはいうまでもなく、放送もデジタル化されたため、両方ともデジタル情報を扱う共通の基盤ができました。
したがって、そこに流れるコンテンツはデジタル情報が中身になります。つまり流れるコンテンツや提供されるサービスも、これに関連するビジネスも、通信と放送両方の基盤を視野に入れることになります。
もうひとつ大事なことは、デジタル・コンテンツをつくる人たちが、放送と通信という2つのフィールドをもてることですね。これは、個人的にも期待が大きいところなのです。
—放送と通信は、どこが違うのでしょうか?
村井 放送(ブロードキャスト)というのは、放送局からコンテンツ(番組)を電波に乗せて、ポンと送るとみんなに送ることができます。これは、インターネットではできないことです。ポンとサーバに置いたものをみんなが取っていくという仕組みはインターネットにはあるのですが、「皆さん見てください!」と言って、リアルタイムにみんなが見るという放送の形態は、インターネットでは原理的に不可能です。
インターネットにはマルチキャストという技術はありますが、これはちょっと放送とは違うのです。この違いが、放送(ブロードキャスト)と通信(コミュニケーション)の違いです。これは、制度にも関わる大事な問題です。だから両者はすぐ融合することはありえないので、僕は「調和」(ハーモニー)という言葉を使うようにしています。
これについては、僕も参加した2006年1月~6月にかけて14回開催された「通信・放送の在り方に関する懇談会」(竹中平蔵 総務相主宰 )でも議論した点です。
—両者の違いがわかる身近な例はありますか?

村井 技術的な違いを説明するときには、僕はいつも犬の遠吠えという例を使っています。犬が、「わぉーん」と吠えたとします。そうすると、周りの犬が聞いていて反応するわけです。この場合は、誰が聞いているのかわからない。聞いている犬がいるかいないかわからない。返事はないかもしれない。返事がなくても遠吠えを聞いている犬には伝わっていますね。これがまさに、放送技術としてのブロードキャストなのです。これに正確に対応する技術はインターネットにはないのです。
つまり、インターネットには、「宛先もなくて聞く人もわかってないけれども、デジタル・データを送信する」という仕組みは厳密にはありません。ですから、このような仕組みが加わったとき、コミュニケーション(通信)というのは、多様化して面白くなるわけです。
このようなフィールドができると、デジタル・コンテンツをつくる人はすごく面白くなるだろうし、ビジネスをつくる人も面白いことを考えるようになるだろうし、それぞれが刺激を与えられると思います。
バックナンバー
関連記事

NTTのNGN戦略を聞く(4):NGNとユーザー間の「コラボレーション」の展開
2007年10月9日 0:00
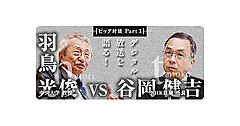
対談:デジタル放送を語る(2):デジタル化で、放送の何が変わったのか?
2006年9月29日 0:00

対談:デジタル放送を語る(1):デジタル化の実現:放送の歴史を変えたMPEG-2
2006年9月21日 0:00

NTTのNGN戦略を聞く(5):世界のNGNの動向と先行するNTTのNGN戦略
2007年10月15日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(11):デジタル放送時代の法制度は?
2008年7月16日 0:00

対談:NGNリリース1と技術的チャレンジを語る(2):世界の通信業界とNGN、そして日本の役割
2007年3月6日 0:00