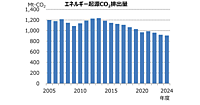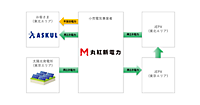対談:放送・通信融合を語る(1):放送と通信はどこがちがうのか?(2ページ目)
【2】アマチュア無線から誕生した「放送」の概念
—亀山先生は、両者の違いをどのようにお考えですか?
亀山 伝統的な通信の話から始めますと、ベルの電話の発明などを含めて、通信の歴史は150年近くになるのです。そもそも当初、通信技術というのは、基本的に無線と有線という2つの大きな技術体系しかありませんでした。
しかし、ある日、無線による通信が実は新しいサービスに使えるということ、つまり単なるポイント・ツー・ポイント(1対1接続)という形式の情報交換ではなくて、ポイント・ツー・マルチポイント(1対多接続)のブロードキャストに使えることに、気が付いた人がいたのです。
書物で読む限りでは、20世紀の初頭の話です。米国のピッツバーグのアマチュア無線家がレコードをかけて、アマチュア無線を使って音楽を流したら、みんな面白くて、「なんだ!こんなので音楽が聴けるんだ!」となった。
それに目をつけたある会社が、アメリカで初めてある周波数帯を商売用に使わせてくれと申請したのが、「ラジオ放送」の始まりだと聞いています。歴史的には、そのときに初めて「放送」という概念が生まれたのです。
—放送と通信は、もともとは一緒だったんですね?
亀山 そうです。基本的には放送と通信は、今日言われているような対立的な概念というのはなくて、根っこがたまたま一緒だったものが、用途から見ると違うものに使えるということだったわけです。
それは先ほど村井先生がおっしゃったように、何もしないでポーンと投げたらドーンと伝わっていくっていうのが、まさしく放送なんですね。たまたま誰かがそういうことに気がついて、放送サービスを始めたのです。ところが、それ以降、ビジネスが展開される中で、いろいろと後付けで規則(ルール)が作られてきたのではないか、と思えるのです。
通信は、基本的にはパイプ(通信回線の容量)が限られていて、秘匿性があるため、ほかの人には聞かれないから何を流してもいいだろうというところがあります。しかし、放送は誰が聞いているのかわからない、つまり不特定多数の人が常に聞いているかもしれない。そこで、やっぱり放送には何らかの規制が必要である、公序良俗に違反するようなことはやってはいけない、ということになったわけです。
しかも電波を使うということになると、電波は有限な資源なので「あなたの会社には、ここの周波数帯に免許を与えて独占的に使えるようにします」というように、そのサービスをスムーズに動かせるために、実は後からいろいろな制度はできてきたのではないかと、歴史を振り返ると思えるのです。
—放送と通信の境界はどこなのでしょうか?

亀山 技術的な観点から見ると、基本的には放送も通信も根っこは一緒であって、たまたま違う媒体あるいは技術、モノを使ったために、お互いに違う方向にサービスが発展してしまったというのが実情なのです。
それは、ある意味でアナログ技術の限界なのですね。つまり、放送がデジタルになった瞬間に、アナログの制約を超えてしまったのです。たとえば、放送(電波)でデジタル技術によってブロードキャストする場合に、上手に暗号方式などを使うと特定の人にも送れるブロードキャストができます。
実際、CS(通信衛星)を使ったCSデジタル放送は、暗号化してデジタル・コンテンツ(番組)を送っているため、これは実は放送ではないという解釈もあります。放送しているのに、「番組を暗号化して、特定多数の人のみが受けられるようにしている」から通信だ、というわけです。
そう考えてみると、もう媒体によって実は通信だとか、放送だというような区別があったアナログ時代はまさにデジタル化を迎え、これに私が関わってきたMPEG(画像圧縮)をはじめとするさまざま技術革新があったために、一気に通信と放送の垣根が取り払われるようになってきました。
旧来の放送媒体を使っても通信はできるし、旧来の通信媒体を使って放送もできる。もちろん村井先生がおっしゃったように、技術的にインターネットのマルチキャストを使うと、リアルタイム性の問題は若干あるにしても、原理的にはどちらの媒体であっても、どちらのサービスも可能な時代になってきているのです。
—つまり、放送と通信は再び一緒のものになっていくのですね?
亀山 放送と通信は、今まさにコンテンツが媒体から独立しつつある(放送媒体でも通信媒体でもコンテンツを流せる)ということと、さらに提供されるサービスが媒体から独立しつつあるということに、直面しているのです。
今、放送と通信の「融合」、あるいは「調和」などと言われているのは、まさしくここから起こってきている現象ではないかと思います。
▽関連リンク
通信・放送の在り方に関する懇談会http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/tsushin_hosou/
関連記事

NTTのNGN戦略を聞く(4):NGNとユーザー間の「コラボレーション」の展開
2007年10月9日 0:00
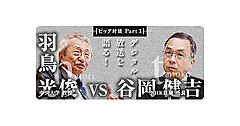
対談:デジタル放送を語る(2):デジタル化で、放送の何が変わったのか?
2006年9月29日 0:00

対談:デジタル放送を語る(1):デジタル化の実現:放送の歴史を変えたMPEG-2
2006年9月21日 0:00

NTTのNGN戦略を聞く(5):世界のNGNの動向と先行するNTTのNGN戦略
2007年10月15日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(11):デジタル放送時代の法制度は?
2008年7月16日 0:00

対談:NGNリリース1と技術的チャレンジを語る(2):世界の通信業界とNGN、そして日本の役割
2007年3月6日 0:00